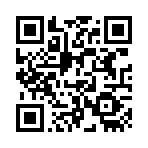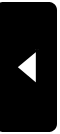中小企業の決算書
2013年10月23日
通常の会計では、現金並びに預金の動きをベースに売上も仕入も管理する。
しかし、期末になると税務申告用の決算のために、売掛金及び買掛金並びに在庫を把握して粗利益を求めることになる。
そうなると、期中で把握していた粗利益が期末では大きく異なってしまう。
また、経費においても現金で出ていく経費しか把握していない場合、減価償却費の計上により大きく営業利益が減ってしまう。もしくは、営業損失となってしまう。
期中の会計処理を現金及び預金取引に基づいて会計帳簿を記帳していた場合の弊害の一部をのべさせてもらいました。
決算書が収益については実現主義、費用については発生主義で作成されるのであれば、日常取引についても現金主義ではなく、収益については実現主義及び費用については発生主義に基づいて会計記帳すべきであると考えます。
その結果が、日々の記帳の成果にも続いて現状を把握し、将来の予測を可能にするからです。
経営者の長年の勘というものは非常に大事ですけれども、勘というものは人についてはうまく説明することが出来ません。
勘を数字に置き換えるためにも日々記帳し、勘が当たっていることを決算書という数字の上でもあらわすことが必要だと思います。
誰に説明するのか?
中小企業においては、金融機関に決算書を見せ融資を受けることが必要なケースが多いです。
この場合において、その時その時のつじつま合わせの決算書を出していれば、あとでぼろが出てしまい、金融機関からの信頼性がなくなってしまいます。金融機関からの信頼がなくなれば融資を容易に受けることが出来ません。
そのためにも、決算書は適正な決算書を作成し、金融機関に対してもいつでも示せるようにすることが必要になってくると思います。
決算書は税務署に提出するためではなく、社内的には将来の予測に資するために、社外的には融資を受ける金融機関の信頼を得るために適切に決算書を作成することが必要になってくると思います。
中小企業にとっての決算書を利用するのは、経営者、金融機関、税務署等の限られた利害関係者になりますので、高度な会計基準は必要ないということもいえます。
より簡便な会計基準として、『中小企業の会計に関する基本要領』(中小会計要領)があります。そして、上場会社の使用する会計基準を簡便にし中小企業に適用可能として会計基準として『中小企業に関する会計指針』(中小企業会計指針)があります。
ある程度規模の大きい中堅企業や上場を目指す企業においては中小企業会計指針を採用し、それ以外の企業においては中小会計要領に従った決算書をつくる必要があると思います。
しかし、期末になると税務申告用の決算のために、売掛金及び買掛金並びに在庫を把握して粗利益を求めることになる。
そうなると、期中で把握していた粗利益が期末では大きく異なってしまう。
また、経費においても現金で出ていく経費しか把握していない場合、減価償却費の計上により大きく営業利益が減ってしまう。もしくは、営業損失となってしまう。
期中の会計処理を現金及び預金取引に基づいて会計帳簿を記帳していた場合の弊害の一部をのべさせてもらいました。
決算書が収益については実現主義、費用については発生主義で作成されるのであれば、日常取引についても現金主義ではなく、収益については実現主義及び費用については発生主義に基づいて会計記帳すべきであると考えます。
その結果が、日々の記帳の成果にも続いて現状を把握し、将来の予測を可能にするからです。
経営者の長年の勘というものは非常に大事ですけれども、勘というものは人についてはうまく説明することが出来ません。
勘を数字に置き換えるためにも日々記帳し、勘が当たっていることを決算書という数字の上でもあらわすことが必要だと思います。
誰に説明するのか?
中小企業においては、金融機関に決算書を見せ融資を受けることが必要なケースが多いです。
この場合において、その時その時のつじつま合わせの決算書を出していれば、あとでぼろが出てしまい、金融機関からの信頼性がなくなってしまいます。金融機関からの信頼がなくなれば融資を容易に受けることが出来ません。
そのためにも、決算書は適正な決算書を作成し、金融機関に対してもいつでも示せるようにすることが必要になってくると思います。
決算書は税務署に提出するためではなく、社内的には将来の予測に資するために、社外的には融資を受ける金融機関の信頼を得るために適切に決算書を作成することが必要になってくると思います。
中小企業にとっての決算書を利用するのは、経営者、金融機関、税務署等の限られた利害関係者になりますので、高度な会計基準は必要ないということもいえます。
より簡便な会計基準として、『中小企業の会計に関する基本要領』(中小会計要領)があります。そして、上場会社の使用する会計基準を簡便にし中小企業に適用可能として会計基準として『中小企業に関する会計指針』(中小企業会計指針)があります。
ある程度規模の大きい中堅企業や上場を目指す企業においては中小企業会計指針を採用し、それ以外の企業においては中小会計要領に従った決算書をつくる必要があると思います。
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。