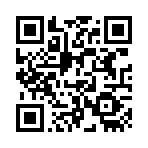税務申告用の財務諸表と金融機関に公表する財務諸表の違い
2017年07月14日
財務会計は外部の公表用の会計であり、ある程度会計ルールに従って作成する必要があります。
中小企業にとっては、大多数が同族企業であり、外部の利害関係者がほとんどいません。外部の利害関係者として意識するのは、税務署と金融機関だけになると思います。
補助金をもらおうとすれば、政府その外部団体という所になるということでしょうか。
ただ、やはり大きく意識するのは税務署であり金融機関です。
ここで、税務用の財務諸表と金融機関が求める財務諸表は異なってきます。
税務としては課税の公平性か一定の法人税法上の処理に従って作成された財務諸表が求められます。そのため、金融機関が企業に求める財務の健全性と相反する処理が求められることになります。例えば、回収可能性がほとんど見込めない売掛金についても税務上貸倒処理がするのが難しいケースがおおいです。また、販売見込みの乏しい棚卸資産についても評価減をすることが容易にはできません。固定資産の減価償却費についても税務上は任意償却であり、償却限度額までの償却が認められるにすぎません。そのため、多額の欠損金を有する企業においては減価償却を行わず欠損金の解消から始めます。このため、法人税法上の処理にしたがって処理された財務諸表は、必ずしも財務健全性を表示しているとはいえません。金融機関が財務の健全性を企業の財務諸表に求めるとの視点で考えれば、法人税法上の会計処理に従って作成された財務諸表は必ずしも財務健全性を示しているといえないことになります。
中小企業の財務諸表はあくまで金融機関が求める財務諸表の健全性を表す財務諸表であり、法人税法上損金に認められない費用については加算していく必要があるんでしょうね。
ただ、多額の欠損金を抱えている企業にとっては償却限度額まで減価償却を行い赤字を膨らませることは、繰越欠損金の期限切れという問題を発生させるため容易に償却限度額までの償却はおこなえないというジレンマを抱えることになります。
中小企業にとっては、大多数が同族企業であり、外部の利害関係者がほとんどいません。外部の利害関係者として意識するのは、税務署と金融機関だけになると思います。
補助金をもらおうとすれば、政府その外部団体という所になるということでしょうか。
ただ、やはり大きく意識するのは税務署であり金融機関です。
ここで、税務用の財務諸表と金融機関が求める財務諸表は異なってきます。
税務としては課税の公平性か一定の法人税法上の処理に従って作成された財務諸表が求められます。そのため、金融機関が企業に求める財務の健全性と相反する処理が求められることになります。例えば、回収可能性がほとんど見込めない売掛金についても税務上貸倒処理がするのが難しいケースがおおいです。また、販売見込みの乏しい棚卸資産についても評価減をすることが容易にはできません。固定資産の減価償却費についても税務上は任意償却であり、償却限度額までの償却が認められるにすぎません。そのため、多額の欠損金を有する企業においては減価償却を行わず欠損金の解消から始めます。このため、法人税法上の処理にしたがって処理された財務諸表は、必ずしも財務健全性を表示しているとはいえません。金融機関が財務の健全性を企業の財務諸表に求めるとの視点で考えれば、法人税法上の会計処理に従って作成された財務諸表は必ずしも財務健全性を示しているといえないことになります。
中小企業の財務諸表はあくまで金融機関が求める財務諸表の健全性を表す財務諸表であり、法人税法上損金に認められない費用については加算していく必要があるんでしょうね。
ただ、多額の欠損金を抱えている企業にとっては償却限度額まで減価償却を行い赤字を膨らませることは、繰越欠損金の期限切れという問題を発生させるため容易に償却限度額までの償却はおこなえないというジレンマを抱えることになります。
棚卸資産について
2014年06月10日
最終仕入原価法は、期末に最も近いときに取得した棚卸資産の一単位当たりの取得価額をもって期末棚卸資産の一単位当たりの取得価額とする方法である。法人税法が定めている棚卸資産の評価方法の一つである。
最終仕入原価法は最終で仕入れた原価がそれ以前で仕入れた原価よりも上回ってしまったときに棚卸資産が仕入原価よりも上回って評価されることにつながるおそれがある。このため、現行の会計制度が取得原価主義の枠内において形成されていることを考えれば、最終仕入原価法で評価した棚卸資産は取得原価より上回るおそれがあるため、会計の面からは最終仕入原価法は認められない。
ただし、棚卸資産の受払について継続的に記録していない場合は、棚卸資産の評価としては最終で仕入れた商品単価に期末で実地棚卸により把握した数量を乗ずることで期末棚卸資産を評価することになる。すなわち、最終仕入原価法は、棚卸計算法と結びつく評価方法であるといえる。
一方、継続的に棚卸の受払を記録していく方法を継続記録法というが、この場合において払出価格をいくらにするかという方法に個別法・先入先出法・平均法・売価還元法がある。
売価還元法に関しては、期中においては払出単価をその都度把握する必要がなく棚卸の数量の受払のみを把握していればいい。
期末において実際の棚卸資産の数量を確認する必要があるため、継続記録法を採用している場合であっても実地棚卸をする必要がある。そして、実地棚卸において把握した棚卸資産の数量と帳簿の数量の差異を把握し、差異分析を実施する。この差異分析により、棚卸資産が盗難に遭ったのか、私的流用されているとかの原因が追求できる。
一方、棚卸計算法を採用している場合においては、帳簿によりあるべき期末棚卸の数量がわからないため、実際に売上のために出荷した棚卸であるか、盗難のための棚卸であるのかが把握できない。
経営管理の面からも継続記録法により棚卸資産の数量を把握することが望ましいといえる。
法人が棚卸資産について、その評価方法を届け出なかった場合、法人税法上は、最終仕入原価法による取得原価によって評価額を計算することになっていることを考慮すると、法人税法上は棚卸計算法を採用することを前提としていると考えられる。
会計的には、棚卸資産については継続記録法を前提として個別法・先入先出法・平均法・売価還元法といった原価法が認められていることを考えると、最終仕入原価法についても例外的に認めるということにすべきであると考えられる。また、帳簿の一種である在庫の受払簿を間接的に作成しなくてもいいと認めることにつながるため、最終仕入原価法を認めることは望ましくないといえる。あくまで、重要性の乏しい棚卸資産についてのみ最終仕入原価法を認めるべきであろう。
最終仕入原価法は最終で仕入れた原価がそれ以前で仕入れた原価よりも上回ってしまったときに棚卸資産が仕入原価よりも上回って評価されることにつながるおそれがある。このため、現行の会計制度が取得原価主義の枠内において形成されていることを考えれば、最終仕入原価法で評価した棚卸資産は取得原価より上回るおそれがあるため、会計の面からは最終仕入原価法は認められない。
ただし、棚卸資産の受払について継続的に記録していない場合は、棚卸資産の評価としては最終で仕入れた商品単価に期末で実地棚卸により把握した数量を乗ずることで期末棚卸資産を評価することになる。すなわち、最終仕入原価法は、棚卸計算法と結びつく評価方法であるといえる。
一方、継続的に棚卸の受払を記録していく方法を継続記録法というが、この場合において払出価格をいくらにするかという方法に個別法・先入先出法・平均法・売価還元法がある。
売価還元法に関しては、期中においては払出単価をその都度把握する必要がなく棚卸の数量の受払のみを把握していればいい。
期末において実際の棚卸資産の数量を確認する必要があるため、継続記録法を採用している場合であっても実地棚卸をする必要がある。そして、実地棚卸において把握した棚卸資産の数量と帳簿の数量の差異を把握し、差異分析を実施する。この差異分析により、棚卸資産が盗難に遭ったのか、私的流用されているとかの原因が追求できる。
一方、棚卸計算法を採用している場合においては、帳簿によりあるべき期末棚卸の数量がわからないため、実際に売上のために出荷した棚卸であるか、盗難のための棚卸であるのかが把握できない。
経営管理の面からも継続記録法により棚卸資産の数量を把握することが望ましいといえる。
法人が棚卸資産について、その評価方法を届け出なかった場合、法人税法上は、最終仕入原価法による取得原価によって評価額を計算することになっていることを考慮すると、法人税法上は棚卸計算法を採用することを前提としていると考えられる。
会計的には、棚卸資産については継続記録法を前提として個別法・先入先出法・平均法・売価還元法といった原価法が認められていることを考えると、最終仕入原価法についても例外的に認めるということにすべきであると考えられる。また、帳簿の一種である在庫の受払簿を間接的に作成しなくてもいいと認めることにつながるため、最終仕入原価法を認めることは望ましくないといえる。あくまで、重要性の乏しい棚卸資産についてのみ最終仕入原価法を認めるべきであろう。
会計、所得、収支の相違について
2014年06月02日
会計、法人税法上の取扱い、資金繰りの計算の3者で取扱いが大きく異なるのが、固定資産、特に減価償却費です。
資金繰りの計算においては減価償却費事態は影響を与えません。固定資産を購入したときに資金が企業から流出していくだけですから、その時に支出として計上するしかないです。
しかし、固定資産は購入したときにそのものを消費するのでなく、所有する期間において効果を及ぼすものであり、また価値が減少していくものであるから、その期間に応じて費用を配分する必要が出てきます。その配分する方法を減価償却といい、企業会計においては必ず減価償却は計上しなければならないもです。
一方、法人税法においては、減価償却を適正に行わせるためにも、減価償却の計算に関する基本的事項すべてについて法定し、「償却限度額」の枠内において減価償却の損金参入を行うべきであるとされています。ただ、損金経理を行うことは企業の任意であることから、必ずしも減価償却を行わなくてもいいともとらえかねない危険性を持っています。
このように、減価償却は、企業会計上は必ず計上すべきでありますが、法人税法上は任意で計上すべきものであり、一方、資金繰りの計算上は全く計算に影響を及ぼすものではありません。
しかし、減価償却のもととなる固定資産の購入のためには多額の金額が必要であることから、資金繰りの観点からも資金の内部留保の効果のある減価償却は毎期計上すべきでしょう。それに、赤字であるから減価償却できないと入ってもその期だけの問題であり、法人税法上の繰越欠損金の利用を通じて間接的に内部留保の効果があらわれることからも、やはり継続して減価償却を計上すべきであると考えます。
資金繰りの計算においては減価償却費事態は影響を与えません。固定資産を購入したときに資金が企業から流出していくだけですから、その時に支出として計上するしかないです。
しかし、固定資産は購入したときにそのものを消費するのでなく、所有する期間において効果を及ぼすものであり、また価値が減少していくものであるから、その期間に応じて費用を配分する必要が出てきます。その配分する方法を減価償却といい、企業会計においては必ず減価償却は計上しなければならないもです。
一方、法人税法においては、減価償却を適正に行わせるためにも、減価償却の計算に関する基本的事項すべてについて法定し、「償却限度額」の枠内において減価償却の損金参入を行うべきであるとされています。ただ、損金経理を行うことは企業の任意であることから、必ずしも減価償却を行わなくてもいいともとらえかねない危険性を持っています。
このように、減価償却は、企業会計上は必ず計上すべきでありますが、法人税法上は任意で計上すべきものであり、一方、資金繰りの計算上は全く計算に影響を及ぼすものではありません。
しかし、減価償却のもととなる固定資産の購入のためには多額の金額が必要であることから、資金繰りの観点からも資金の内部留保の効果のある減価償却は毎期計上すべきでしょう。それに、赤字であるから減価償却できないと入ってもその期だけの問題であり、法人税法上の繰越欠損金の利用を通じて間接的に内部留保の効果があらわれることからも、やはり継続して減価償却を計上すべきであると考えます。
確定申告の受付が始まりましたね
2014年02月17日
おはようございます。
確定申告の受付が今日2月17日(月)が始まりました。
還付申告についての受付は、すでに始まってます。
所得税及び復興特別税並びに贈与税の申告及び納付は3月17日(月)までです。
3月15日が土曜日であったために、申告期限が17日まで延長となっています。
個人事業者の消費税及び地方消費税の申告及び納付は3月31日(月)までです。
預金からの振替納税をされている方においては、申告所得税及び復興特別所得税の振替日は平成26年4月22日(火)、消費税及び地方消費税の振替日は平成26年4月24日(木)です。
確定申告の受付が今日2月17日(月)が始まりました。
還付申告についての受付は、すでに始まってます。
所得税及び復興特別税並びに贈与税の申告及び納付は3月17日(月)までです。
3月15日が土曜日であったために、申告期限が17日まで延長となっています。
個人事業者の消費税及び地方消費税の申告及び納付は3月31日(月)までです。
預金からの振替納税をされている方においては、申告所得税及び復興特別所得税の振替日は平成26年4月22日(火)、消費税及び地方消費税の振替日は平成26年4月24日(木)です。
相続税法改正について思うこと
2014年02月10日
おはようございます。
平成25年度税制改正により相続税が改正され、平成27年1月1日から施行されます。
相続税の改正のうち、大きな改正としては4点あります。
第一点は、遺産に係る基礎控除額が引き下げられます。
第二点は、最高税率の引上げなど税率の構造が変わります。
第三点は、税額控除の改正が行われまして、未成年者控除及び障害者控除の控除額が引き上げられます。
第四点は、小規模宅地等の特例が改正され、居住用の宅地等(特定居住用宅地等)の限度面積及び居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積が拡大されます。
これらの相続税の改正のうち、私が気になるのは遺産に係る基礎控除額の引き下げに関してです。従来は遺産総額に係る基礎控除額は、5000万円+(1000万円×法定相続人の数)で求められました。しかし、改正後は全体的に現行の6割に引き下げられ、3000万円+(600万円×法定相続人の数)となりました。
例えば、従来でしたら、夫が亡くなり、妻と子供2人が相続人であった場合、基礎控除額は5000万円+1000万円×3=8000万円であったのが、改正後は3000万円+600万円×3=4800万円となります。仮に遺産相続が5000万円であったとしたら、従来は相続税の申告が必要なかったのが、改正後は相続税の申告が必要となってきます。相続税がかかるかどうかという点については、配偶者控除や小規模宅地等の特例を使えば、相続税がかからなくなるかもしれません。しかし、課配偶者控除や小規模宅地等の特例を使うにあたっても相続税の申告期限である10ヶ月以内に遺産分割協議書を作成し、相続税の申告を行う必要が出てきます。すなわち、従来ならば、相続税の申告自体が必要ないということで遺産分割にしても被相続人がなくなって、1周忌が終わってから遺産をどうするのか本格的に相談していても問題がなかった家族に関しても、遺産総額に係る基礎控除を越える可能性が出てきましたので、相続税の改正後は相続税の申告を考える必要が出てきます。
1周忌が終わってから、遺産分割の話をしているのでは遅くなってきます。せめて、満中陰が終わるまでには被相続人の遺産の総額を把握し、遺産に係る基礎控除額を越えるかどうか、越える場合には遺産分割をどのようにすすめていくのかを検討し、早めに税理士さんに相続の申告についての相談を行うべきだと思います。
被相続人がなくなって8ヶ月もたってから遺産をどのように分割し相続の申告をしようとの相談をされても、遺産総額の把握及び遺産分割に時間がかかり、相続の申告までに遺産分割がまとまらない可能性がありますから、早めのご相談をお願いいたします。
平成25年度税制改正により相続税が改正され、平成27年1月1日から施行されます。
相続税の改正のうち、大きな改正としては4点あります。
第一点は、遺産に係る基礎控除額が引き下げられます。
第二点は、最高税率の引上げなど税率の構造が変わります。
第三点は、税額控除の改正が行われまして、未成年者控除及び障害者控除の控除額が引き上げられます。
第四点は、小規模宅地等の特例が改正され、居住用の宅地等(特定居住用宅地等)の限度面積及び居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積が拡大されます。
これらの相続税の改正のうち、私が気になるのは遺産に係る基礎控除額の引き下げに関してです。従来は遺産総額に係る基礎控除額は、5000万円+(1000万円×法定相続人の数)で求められました。しかし、改正後は全体的に現行の6割に引き下げられ、3000万円+(600万円×法定相続人の数)となりました。
例えば、従来でしたら、夫が亡くなり、妻と子供2人が相続人であった場合、基礎控除額は5000万円+1000万円×3=8000万円であったのが、改正後は3000万円+600万円×3=4800万円となります。仮に遺産相続が5000万円であったとしたら、従来は相続税の申告が必要なかったのが、改正後は相続税の申告が必要となってきます。相続税がかかるかどうかという点については、配偶者控除や小規模宅地等の特例を使えば、相続税がかからなくなるかもしれません。しかし、課配偶者控除や小規模宅地等の特例を使うにあたっても相続税の申告期限である10ヶ月以内に遺産分割協議書を作成し、相続税の申告を行う必要が出てきます。すなわち、従来ならば、相続税の申告自体が必要ないということで遺産分割にしても被相続人がなくなって、1周忌が終わってから遺産をどうするのか本格的に相談していても問題がなかった家族に関しても、遺産総額に係る基礎控除を越える可能性が出てきましたので、相続税の改正後は相続税の申告を考える必要が出てきます。
1周忌が終わってから、遺産分割の話をしているのでは遅くなってきます。せめて、満中陰が終わるまでには被相続人の遺産の総額を把握し、遺産に係る基礎控除額を越えるかどうか、越える場合には遺産分割をどのようにすすめていくのかを検討し、早めに税理士さんに相続の申告についての相談を行うべきだと思います。
被相続人がなくなって8ヶ月もたってから遺産をどのように分割し相続の申告をしようとの相談をされても、遺産総額の把握及び遺産分割に時間がかかり、相続の申告までに遺産分割がまとまらない可能性がありますから、早めのご相談をお願いいたします。