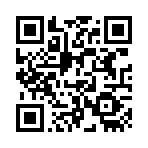ライフネット生命の出口代表取締役会長兼CEOの話を聞いて
2014年02月16日
私は公認会計士・税理士の資格の他にFPの資格の一つであるAFPの資格を有しています。
SG滋賀に昨年の12月から正式に入会しているのですが、先日の2月の定例会においてライフネット生命の出口代表取締役会長兼CEOの講演がありました。
出口会長の講演内容で興味が引かれる部分がありましたのでここで講演内容の一部をアップしたいと思います。
生命保険の将来として、少子高齢化及び1940年体制からの脱却という2つの前提において話を進められていました。
少子高齢化についは、出口さんの講演以外にも様々なところで話を聞いていました。企業にとっては日本国内において既存のターゲット層の需要が減っていくことを意味します。
このブログで詳しく取り上げたいのは、1940年体制からの脱却のほうです。
1940年体制とは護送船団方式に代表される大蔵省の一元指導の体制のことです。生命保険会社にとっては、保険料も商品も原則同一だったため、商品を比較しようという発生がそもそも生じなくなり、数は力であるという信奉が生まれていくという帰結になってしまったということです。
これが、1995年に保険業法が改正され、生命保険が自由化になると、保険の商品も自由になり、保険料も自由化になった結果、同一商品では保険料だけの差別化となるため、商品自体を複雑化していくことになります。しかし、その保険商品を説明できるだけの人材がいなかったために、説明不足に陥りその結果として保険の不払い問題が起こったのではないかという説明でした。
このことは、商品を複雑にして単なる差別化から脱することはいいのですが、その複雑化した商品を売るためにはその売るための能力も求められてくるということです。
また、既存の環境が変わっていく中で、それでも価値観の変化が十分図れていないのが現状ではないのか、このような話をされていました。
これは、会計の世界にもいえることだと思います。
高度成長期が終わり、売上だけを求めるのでなく、利益を考えて経営していくことが求められているはずなのに、いまだに記帳代行をたのみ、利益の把握を勘だけでしている経営者が多いということは環境変化において頭でわかっていても本当には行動にまでは移せていない経営者が多いということなのではないかと思います。
SG滋賀に昨年の12月から正式に入会しているのですが、先日の2月の定例会においてライフネット生命の出口代表取締役会長兼CEOの講演がありました。
出口会長の講演内容で興味が引かれる部分がありましたのでここで講演内容の一部をアップしたいと思います。
生命保険の将来として、少子高齢化及び1940年体制からの脱却という2つの前提において話を進められていました。
少子高齢化についは、出口さんの講演以外にも様々なところで話を聞いていました。企業にとっては日本国内において既存のターゲット層の需要が減っていくことを意味します。
このブログで詳しく取り上げたいのは、1940年体制からの脱却のほうです。
1940年体制とは護送船団方式に代表される大蔵省の一元指導の体制のことです。生命保険会社にとっては、保険料も商品も原則同一だったため、商品を比較しようという発生がそもそも生じなくなり、数は力であるという信奉が生まれていくという帰結になってしまったということです。
これが、1995年に保険業法が改正され、生命保険が自由化になると、保険の商品も自由になり、保険料も自由化になった結果、同一商品では保険料だけの差別化となるため、商品自体を複雑化していくことになります。しかし、その保険商品を説明できるだけの人材がいなかったために、説明不足に陥りその結果として保険の不払い問題が起こったのではないかという説明でした。
このことは、商品を複雑にして単なる差別化から脱することはいいのですが、その複雑化した商品を売るためにはその売るための能力も求められてくるということです。
また、既存の環境が変わっていく中で、それでも価値観の変化が十分図れていないのが現状ではないのか、このような話をされていました。
これは、会計の世界にもいえることだと思います。
高度成長期が終わり、売上だけを求めるのでなく、利益を考えて経営していくことが求められているはずなのに、いまだに記帳代行をたのみ、利益の把握を勘だけでしている経営者が多いということは環境変化において頭でわかっていても本当には行動にまでは移せていない経営者が多いということなのではないかと思います。
中小企業の会計に関する指針
2014年02月05日
中小企業においては、主に税法に従った会計処理が行われていました。
会計基準については、上場会社が従うものとしてとられており、実際中小企業が『企業会計原則』その他会計基準に従った決算書を作っていることは乏しかったと思います。
金融ビックバンをきっかけに、会計制度の改革は、激しいものがあります。
そして、会計と税法の隔離も従来以上に大きくなってきております。そのため、税法に従った決算書が会計の側面から見て適正な決算書といえなくなってきました。その原因としては、中小企業に適正な会計基準がなかったからだと思います。
そこで、日本公認会計士協会・日本税理士会連合会・日本商工会議所・会計基準委員会が協議し、『中小企業の会計に関する指針』を作成しました。
会計基準は毎月のように制度変更があり、会社法の施行がなされる中、『中小企業の会計に関する指針』も変更を余儀なくされていっております。結果として、『中小企業の会計に関する指針』も毎年変更となることになっております。
なお、『中小企業の会計に関する指針』に従った決算書を作成し、日本税理士連合会から出しているチェックリストを付して提出した場合、融資に際して優遇税率の適用が受けられる可能性もあります。
会計基準については、上場会社が従うものとしてとられており、実際中小企業が『企業会計原則』その他会計基準に従った決算書を作っていることは乏しかったと思います。
金融ビックバンをきっかけに、会計制度の改革は、激しいものがあります。
そして、会計と税法の隔離も従来以上に大きくなってきております。そのため、税法に従った決算書が会計の側面から見て適正な決算書といえなくなってきました。その原因としては、中小企業に適正な会計基準がなかったからだと思います。
そこで、日本公認会計士協会・日本税理士会連合会・日本商工会議所・会計基準委員会が協議し、『中小企業の会計に関する指針』を作成しました。
会計基準は毎月のように制度変更があり、会社法の施行がなされる中、『中小企業の会計に関する指針』も変更を余儀なくされていっております。結果として、『中小企業の会計に関する指針』も毎年変更となることになっております。
なお、『中小企業の会計に関する指針』に従った決算書を作成し、日本税理士連合会から出しているチェックリストを付して提出した場合、融資に際して優遇税率の適用が受けられる可能性もあります。
利益管理について
2014年02月05日
利益管理をどのように行うべきか?
それも人での少ない中小企業において。
非常に難しい問題だと思います。
まず、大手企業と違い、月次決算を適時に行うだけの能力を有する人材が経理にいない。そのために、月次決算においてはやくても1月遅れで出来ればいい方だと思います。
しかし、原材料の値上がりが多くなっている昨今では原材料の値上がり分を販売単価に転嫁していかないと利益を確保できなくなります。そのためには適時に利益管理を行い価格に転嫁できるように原価管理を行う必要があります。しかし、月次決算を待っての利益管理を行おうとすれば、どうしても適時の判断が出来なくなりと思われます。
そこで、原価管理を適時に行うためにも、売上の日々の監理と原材料の仕入額の監理が必要になります。すなわち、原材料については、出来るだけ仕入時点で購入額を把握し、当期の売り上げと対応させることで、粗利の把握を適時にする必要があります。この管理方法は、必要なソフトを使ってもいいでしょうし、エクセルで管理することも一つだと思います。例えばエクセルでの管理方法としては、売上については現金売り、掛け売りの管理を行い、仕入についても現金仕入、掛け仕入の管理を行うことも必要でしょう。すなわち、会計での管理ではなく帳簿外での管理でもいいので、適時に粗利益の管理を行うことが必要だと考えます。
なお、製造業については原材料の仕入に見込経費を加算し予定原価を算定することで、原価管理を行っていくことも有意義だと考えます。
当事務所においては、このような原価管理の指導もいたしますので、希望の方は事務所までご連絡ください。
それも人での少ない中小企業において。
非常に難しい問題だと思います。
まず、大手企業と違い、月次決算を適時に行うだけの能力を有する人材が経理にいない。そのために、月次決算においてはやくても1月遅れで出来ればいい方だと思います。
しかし、原材料の値上がりが多くなっている昨今では原材料の値上がり分を販売単価に転嫁していかないと利益を確保できなくなります。そのためには適時に利益管理を行い価格に転嫁できるように原価管理を行う必要があります。しかし、月次決算を待っての利益管理を行おうとすれば、どうしても適時の判断が出来なくなりと思われます。
そこで、原価管理を適時に行うためにも、売上の日々の監理と原材料の仕入額の監理が必要になります。すなわち、原材料については、出来るだけ仕入時点で購入額を把握し、当期の売り上げと対応させることで、粗利の把握を適時にする必要があります。この管理方法は、必要なソフトを使ってもいいでしょうし、エクセルで管理することも一つだと思います。例えばエクセルでの管理方法としては、売上については現金売り、掛け売りの管理を行い、仕入についても現金仕入、掛け仕入の管理を行うことも必要でしょう。すなわち、会計での管理ではなく帳簿外での管理でもいいので、適時に粗利益の管理を行うことが必要だと考えます。
なお、製造業については原材料の仕入に見込経費を加算し予定原価を算定することで、原価管理を行っていくことも有意義だと考えます。
当事務所においては、このような原価管理の指導もいたしますので、希望の方は事務所までご連絡ください。
自計化について
2014年02月05日
自計化を行うのは、会社にとっては非常に有意義なことだと考えます。
会計は、会計事務所に完全に任せている場合、決算後でしか会社の業績が把握できず、売上、仕入及び経費からだいたいの金額を把握するだけでしかなく、節税などの税務対策もついつい後手後手に回ってしまいできなくなります。
自社で、記帳を行う場合、適時に会社の業績を把握できるようにになるため、上記の節税対策も機動的に行うことができます。
それに、月次での状況を把握することで投資の判断についても金額での予測を行いながらすることが可能になります。
会計事務所には月次の決算を行う場合においては月次でのレビューをお願いするなどして適時の判断をお願いすることが望ましいと思います。
毎月、会計事務所にいつもとは違うことについては伝えておかないと決算でのチェックの段階で問題が発見されるケースも出てきます。
これは、自計化する上での問題点ですかね。
そのため、自計化するから顧問料はいらないということにはならないと思います。自計化をしても、毎月の会計事務所でのチェックをお願いしない限りは会社での判断ミスは見つからないと思いますし・・・。
結局、自計化=会計事務所に対する経費削減とはいかないんですね。
適時な判断が可能であるとの考えをもって、自計化を行うのがいいのでしょう。
会計は、会計事務所に完全に任せている場合、決算後でしか会社の業績が把握できず、売上、仕入及び経費からだいたいの金額を把握するだけでしかなく、節税などの税務対策もついつい後手後手に回ってしまいできなくなります。
自社で、記帳を行う場合、適時に会社の業績を把握できるようにになるため、上記の節税対策も機動的に行うことができます。
それに、月次での状況を把握することで投資の判断についても金額での予測を行いながらすることが可能になります。
会計事務所には月次の決算を行う場合においては月次でのレビューをお願いするなどして適時の判断をお願いすることが望ましいと思います。
毎月、会計事務所にいつもとは違うことについては伝えておかないと決算でのチェックの段階で問題が発見されるケースも出てきます。
これは、自計化する上での問題点ですかね。
そのため、自計化するから顧問料はいらないということにはならないと思います。自計化をしても、毎月の会計事務所でのチェックをお願いしない限りは会社での判断ミスは見つからないと思いますし・・・。
結局、自計化=会計事務所に対する経費削減とはいかないんですね。
適時な判断が可能であるとの考えをもって、自計化を行うのがいいのでしょう。
決算対策へのスタンス
2014年02月05日
知り合いの経営者と話していると、節税の話になることが多いです。
そこで、節税に対する対応策としての私のスタンスを書かせていただきます。
以前のブログにも書かせていただいていたことの繰り返しになると思いますが、企業にとって月次決算は大企業のみならず中小企業にとっても必要だと考えています。
節税は、決算が終了した後に行うことはできません。
決算が来る前に、当期の利益を予想し、その予想に対して、新たな設備投資を始めるなり、保険をかけるなり、いろいろと決算に向けて考えることが、最終的に節税なりにつながっていくのではないでしょうか?
そのためには、できれば月次決算を行うようにすることが常に利益を見ながら設備投資などの経営判断ができるので有効ではないでしょうか?
月次決算ができなくとも、3ヶ月に1回決算をしめることが有効だと思います。
特に、9ヶ月を経過した段階での決算は、1年間の決算を予想し、決算対策なりを企業として図ることができると思います。
ただし、この第3四半期の決算は、せめてい、12ヶ月目に入る前に月次決算をしめてしまいましょう。
そうでないと、折角9ヶ月で決算をしめたのに決算対策ができない結果になってしまいますから・・・。
そこで、節税に対する対応策としての私のスタンスを書かせていただきます。
以前のブログにも書かせていただいていたことの繰り返しになると思いますが、企業にとって月次決算は大企業のみならず中小企業にとっても必要だと考えています。
節税は、決算が終了した後に行うことはできません。
決算が来る前に、当期の利益を予想し、その予想に対して、新たな設備投資を始めるなり、保険をかけるなり、いろいろと決算に向けて考えることが、最終的に節税なりにつながっていくのではないでしょうか?
そのためには、できれば月次決算を行うようにすることが常に利益を見ながら設備投資などの経営判断ができるので有効ではないでしょうか?
月次決算ができなくとも、3ヶ月に1回決算をしめることが有効だと思います。
特に、9ヶ月を経過した段階での決算は、1年間の決算を予想し、決算対策なりを企業として図ることができると思います。
ただし、この第3四半期の決算は、せめてい、12ヶ月目に入る前に月次決算をしめてしまいましょう。
そうでないと、折角9ヶ月で決算をしめたのに決算対策ができない結果になってしまいますから・・・。