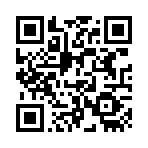経営者にとって必要な利益管理とは?
2017年07月27日
経営者にとっては、融資を受けるために直近の売上及び利益の金額が必要になっております。そのための一つとして、売上を管理するためには、販売管理が必要になります。
この販売管理については、経理の数字から離れて販売管理システム(そんなにたいそうな言葉を言っていますが、エクセルで売り上げの管理をしてもいいと思います)による管理が出来ていれば十分だと思います。
ただし、高度成長期においては、売れれば当然利益も確保出来ていた時代ですから、販売管理だけで十分だったようです。
しかし、バブル崩壊後、特に中小企業にとっては、中国が経済的に成長しだしてからは、単価の値下げに伴い、売上が増加してもそれ以上に赤字が増大している可能性も大いにあります。結果として、販売管理のみならず、利益管理までも必要になってきました。
利益管理を行おうとすれば、当然減価償却や貸し倒れ引当金の影響など、中小企業にとっては決算時にしか行っていなかった処理も月次に行うことが必要となります。
適時に利益管理を行うためには、当然決算だけでの管理だと十分とはいえません。月次決算が必要になります。また、利益管理ということですから、年1回の決算に影響してくる減価償却も12で割って、概算でもいいですから、月次決算に落とし込む必要があります。また、月次の棚卸資産も概算で計上する必要が出てきます。そのうえ、売掛金、買掛金の把握も毎月行う必要があります。さらには、未払金、前払金の把握も行う必要がありますが、この把握については、毎月行うのは大変でしょうから、金額の影響を及ぼすものについてのみ行えば十分でしょう。
利益管理を行うことによって、企業にとっては、融資を受けやすくなりますし、適時に経営を把握できますから、設備投資や修繕などの判断も適時に適切に行うことが可能になると思います。
そして、適時に利益管理を行うためには、会計事務所や外部の計算センターに会計処理を依頼するのは望ましくなく、自分の企業において自計化を行うべきです。
企業にとっては自計化でより早く適時に利益を把握することが最も重要ではないでしょうか?
この販売管理については、経理の数字から離れて販売管理システム(そんなにたいそうな言葉を言っていますが、エクセルで売り上げの管理をしてもいいと思います)による管理が出来ていれば十分だと思います。
ただし、高度成長期においては、売れれば当然利益も確保出来ていた時代ですから、販売管理だけで十分だったようです。
しかし、バブル崩壊後、特に中小企業にとっては、中国が経済的に成長しだしてからは、単価の値下げに伴い、売上が増加してもそれ以上に赤字が増大している可能性も大いにあります。結果として、販売管理のみならず、利益管理までも必要になってきました。
利益管理を行おうとすれば、当然減価償却や貸し倒れ引当金の影響など、中小企業にとっては決算時にしか行っていなかった処理も月次に行うことが必要となります。
適時に利益管理を行うためには、当然決算だけでの管理だと十分とはいえません。月次決算が必要になります。また、利益管理ということですから、年1回の決算に影響してくる減価償却も12で割って、概算でもいいですから、月次決算に落とし込む必要があります。また、月次の棚卸資産も概算で計上する必要が出てきます。そのうえ、売掛金、買掛金の把握も毎月行う必要があります。さらには、未払金、前払金の把握も行う必要がありますが、この把握については、毎月行うのは大変でしょうから、金額の影響を及ぼすものについてのみ行えば十分でしょう。
利益管理を行うことによって、企業にとっては、融資を受けやすくなりますし、適時に経営を把握できますから、設備投資や修繕などの判断も適時に適切に行うことが可能になると思います。
そして、適時に利益管理を行うためには、会計事務所や外部の計算センターに会計処理を依頼するのは望ましくなく、自分の企業において自計化を行うべきです。
企業にとっては自計化でより早く適時に利益を把握することが最も重要ではないでしょうか?
売掛管理について
2017年07月24日
今日は債権管理についてどう考えるかを記載したいと思います。
売上は、受注し、商品を出荷し、先方に請求し、回収するという行為をたどります。
製造業においては、この受注の管理ということがしっかりなされていないと、工程管理ができないことにつながりますので、受注管理も大事になります。卸売業や小売業についても、受注管理は重要ですよね。いくらの受注を受け、手元にいくらの商品があるかということを管理していないといけないです。受注管理とともに当然在庫管理もなされていないといけないですね。
商品を得意先に出荷し、得意先が検品してはじめて得意先に請求することが可能になります。会計上及び税務上は、出荷して売上を計上することになります。出荷即入金が可能なのは小売業ぐらいですから、売掛金/売上の仕訳をきることになります。
月次ごとに請求行為をし、その請求について回収なされているか管理する必要が出てきます。回収の管理まで考えると、手書きでの管理ではなく、やはり販売管理ソフトにおいて販売管理をしていくことが必要になってくるのではないでしょうか?得意先においていくらの売掛債権が残っており、回収不能がどのくらいあるのかまでしっかり管理することが必要ですね。
会計で管理する場合においては月次決算をすることが当然ですが、売掛金については補助科目を取引先ごとに設定し取引先ごとに会計上も管理することも必要です。
特に、債権管理を営業部門が行い、会計を経理部門が行っている場合は会計上の売掛残高と実際の債権残高が一致しているかどうかチェックし、会計上において売上の計上漏れがないかどうかをチェックすることも大事です。また、不明な売掛金残高が残っていないかを会社内での第三者の目で定期的にチェックすることも内部統制の上からも重要だと思います。
売上は、受注し、商品を出荷し、先方に請求し、回収するという行為をたどります。
製造業においては、この受注の管理ということがしっかりなされていないと、工程管理ができないことにつながりますので、受注管理も大事になります。卸売業や小売業についても、受注管理は重要ですよね。いくらの受注を受け、手元にいくらの商品があるかということを管理していないといけないです。受注管理とともに当然在庫管理もなされていないといけないですね。
商品を得意先に出荷し、得意先が検品してはじめて得意先に請求することが可能になります。会計上及び税務上は、出荷して売上を計上することになります。出荷即入金が可能なのは小売業ぐらいですから、売掛金/売上の仕訳をきることになります。
月次ごとに請求行為をし、その請求について回収なされているか管理する必要が出てきます。回収の管理まで考えると、手書きでの管理ではなく、やはり販売管理ソフトにおいて販売管理をしていくことが必要になってくるのではないでしょうか?得意先においていくらの売掛債権が残っており、回収不能がどのくらいあるのかまでしっかり管理することが必要ですね。
会計で管理する場合においては月次決算をすることが当然ですが、売掛金については補助科目を取引先ごとに設定し取引先ごとに会計上も管理することも必要です。
特に、債権管理を営業部門が行い、会計を経理部門が行っている場合は会計上の売掛残高と実際の債権残高が一致しているかどうかチェックし、会計上において売上の計上漏れがないかどうかをチェックすることも大事です。また、不明な売掛金残高が残っていないかを会社内での第三者の目で定期的にチェックすることも内部統制の上からも重要だと思います。
経営計画について
2017年07月17日
今日は経営計画のことについて記載したいと思います。
自分の会社をこういった方向に持っていきたいな。大きな夢としてこういう方向性に持って行ければな。こうした夢や目標をある程度の道筋として目に見える形として落としていくのが長期計画です。壮大な夢でもかまわないと思います。
ただ、この大きな夢は遠すぎるものであるため、もう少し具体的な目標に置き換えていくのが中期計画となります。今の体制では全く夢に向かえなければ夢に向かって体制を整えていく必要があると思います。この体制を整えるのが、2~3年かかるのならば、この2~3年が中期計画の期間となります。それよりももう少しかかるでしょうというので5年計画というのが中期計画の一般的な期間になりますね。
中期計画は具体的な目標でもあるので、粗々でもいいのでもう少し具体的な目標数値が求められてくることになります。
この中期計画を達成するために、まずは目の前の目標を定める必要があります。これが短期経営計画になります。
今は経済環境の変化が激しすぎて、中期計画が立てられないと思われるかもしれません。しかしながら、自分の会社がどの方向に向かうのかを明らかにするためにも中期計画を立てることが必要です。そして、自分の会社を取り巻く環境が変われば、中期計画を見直すことも必要です。この場合に、短期計画も大幅に変える必要があるのでしたら、短期計画も見直す必要があると思います。ただ、短期計画での方向性が当初の計画時と大幅に違わないのでしたら、目の前の目標である短期計画の変更はする必要はないと思います。
会社をどういった方向に持っていくのが具体的に落とし込むためにも経営計画を立てられたらどうでしょうか?
自分の会社をこういった方向に持っていきたいな。大きな夢としてこういう方向性に持って行ければな。こうした夢や目標をある程度の道筋として目に見える形として落としていくのが長期計画です。壮大な夢でもかまわないと思います。
ただ、この大きな夢は遠すぎるものであるため、もう少し具体的な目標に置き換えていくのが中期計画となります。今の体制では全く夢に向かえなければ夢に向かって体制を整えていく必要があると思います。この体制を整えるのが、2~3年かかるのならば、この2~3年が中期計画の期間となります。それよりももう少しかかるでしょうというので5年計画というのが中期計画の一般的な期間になりますね。
中期計画は具体的な目標でもあるので、粗々でもいいのでもう少し具体的な目標数値が求められてくることになります。
この中期計画を達成するために、まずは目の前の目標を定める必要があります。これが短期経営計画になります。
今は経済環境の変化が激しすぎて、中期計画が立てられないと思われるかもしれません。しかしながら、自分の会社がどの方向に向かうのかを明らかにするためにも中期計画を立てることが必要です。そして、自分の会社を取り巻く環境が変われば、中期計画を見直すことも必要です。この場合に、短期計画も大幅に変える必要があるのでしたら、短期計画も見直す必要があると思います。ただ、短期計画での方向性が当初の計画時と大幅に違わないのでしたら、目の前の目標である短期計画の変更はする必要はないと思います。
会社をどういった方向に持っていくのが具体的に落とし込むためにも経営計画を立てられたらどうでしょうか?
変動損益計算書について
2014年07月08日
今日は「変動損益計算書」について述べたいと思います。
利益は当然、以下の式で表されます。
利益=売上-費用
売上を分析すると
売上=販売数量×販売単価であらわされます。
また、費用を分析すると
費用=変動費(=変動費+準変動費)+固定費(=固定費+準固定費)という式になります。
利益=売上-変動費-固定費であらわされる損益計算書を変動損益計算書といいます。
ここで、変動費とは売上高に応じて変動する費用で、固定費とは売上高の増減とは無関係の費用のことをいいます。
そのため、変動費=変動比率×販売数量で表されます。
最初の利益の数式を変動損益計算書の数式に変えると
利益=売上高-変動費-固定費
=(販売数量-変動比率)×販売数量-固定費
以上の数式になります。
すなわち、この数式は固定費を上回る利益をあげることにより、正味の利益が回収できるということをあらわしています。
変動費には売上原価だけではなく、販売費も含まれることになるため、一般の損益計算書に基づいてそのまま変動損益計算書の考え方を当てはめるのは危険です。
売上原価を差し引いたという意味での粗利益が出ているから大丈夫だという事ではなく、販売費も含めた限界利益が出ているかどうかを考えるのかが大事になってきます。
限界利益とは売上高から変動費を差し引いた金額のことをいいます。
限界利益=売上高-変動費
なお、変動損益計算書はあくまで内部管理用の損益計算書であり、外部公表表の損益計算書ではありません。
利益は当然、以下の式で表されます。
利益=売上-費用
売上を分析すると
売上=販売数量×販売単価であらわされます。
また、費用を分析すると
費用=変動費(=変動費+準変動費)+固定費(=固定費+準固定費)という式になります。
利益=売上-変動費-固定費であらわされる損益計算書を変動損益計算書といいます。
ここで、変動費とは売上高に応じて変動する費用で、固定費とは売上高の増減とは無関係の費用のことをいいます。
そのため、変動費=変動比率×販売数量で表されます。
最初の利益の数式を変動損益計算書の数式に変えると
利益=売上高-変動費-固定費
=(販売数量-変動比率)×販売数量-固定費
以上の数式になります。
すなわち、この数式は固定費を上回る利益をあげることにより、正味の利益が回収できるということをあらわしています。
変動費には売上原価だけではなく、販売費も含まれることになるため、一般の損益計算書に基づいてそのまま変動損益計算書の考え方を当てはめるのは危険です。
売上原価を差し引いたという意味での粗利益が出ているから大丈夫だという事ではなく、販売費も含めた限界利益が出ているかどうかを考えるのかが大事になってきます。
限界利益とは売上高から変動費を差し引いた金額のことをいいます。
限界利益=売上高-変動費
なお、変動損益計算書はあくまで内部管理用の損益計算書であり、外部公表表の損益計算書ではありません。
会計、所得、収支の相違について
2014年06月02日
会計、法人税法上の取扱い、資金繰りの計算の3者で取扱いが大きく異なるのが、固定資産、特に減価償却費です。
資金繰りの計算においては減価償却費事態は影響を与えません。固定資産を購入したときに資金が企業から流出していくだけですから、その時に支出として計上するしかないです。
しかし、固定資産は購入したときにそのものを消費するのでなく、所有する期間において効果を及ぼすものであり、また価値が減少していくものであるから、その期間に応じて費用を配分する必要が出てきます。その配分する方法を減価償却といい、企業会計においては必ず減価償却は計上しなければならないもです。
一方、法人税法においては、減価償却を適正に行わせるためにも、減価償却の計算に関する基本的事項すべてについて法定し、「償却限度額」の枠内において減価償却の損金参入を行うべきであるとされています。ただ、損金経理を行うことは企業の任意であることから、必ずしも減価償却を行わなくてもいいともとらえかねない危険性を持っています。
このように、減価償却は、企業会計上は必ず計上すべきでありますが、法人税法上は任意で計上すべきものであり、一方、資金繰りの計算上は全く計算に影響を及ぼすものではありません。
しかし、減価償却のもととなる固定資産の購入のためには多額の金額が必要であることから、資金繰りの観点からも資金の内部留保の効果のある減価償却は毎期計上すべきでしょう。それに、赤字であるから減価償却できないと入ってもその期だけの問題であり、法人税法上の繰越欠損金の利用を通じて間接的に内部留保の効果があらわれることからも、やはり継続して減価償却を計上すべきであると考えます。
資金繰りの計算においては減価償却費事態は影響を与えません。固定資産を購入したときに資金が企業から流出していくだけですから、その時に支出として計上するしかないです。
しかし、固定資産は購入したときにそのものを消費するのでなく、所有する期間において効果を及ぼすものであり、また価値が減少していくものであるから、その期間に応じて費用を配分する必要が出てきます。その配分する方法を減価償却といい、企業会計においては必ず減価償却は計上しなければならないもです。
一方、法人税法においては、減価償却を適正に行わせるためにも、減価償却の計算に関する基本的事項すべてについて法定し、「償却限度額」の枠内において減価償却の損金参入を行うべきであるとされています。ただ、損金経理を行うことは企業の任意であることから、必ずしも減価償却を行わなくてもいいともとらえかねない危険性を持っています。
このように、減価償却は、企業会計上は必ず計上すべきでありますが、法人税法上は任意で計上すべきものであり、一方、資金繰りの計算上は全く計算に影響を及ぼすものではありません。
しかし、減価償却のもととなる固定資産の購入のためには多額の金額が必要であることから、資金繰りの観点からも資金の内部留保の効果のある減価償却は毎期計上すべきでしょう。それに、赤字であるから減価償却できないと入ってもその期だけの問題であり、法人税法上の繰越欠損金の利用を通じて間接的に内部留保の効果があらわれることからも、やはり継続して減価償却を計上すべきであると考えます。