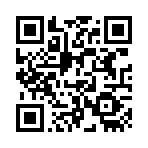中小会計要領~各論その5
2014年07月25日
今日は「中小企業の会計に関する基本要領」の「2.資産、負債の基本的な会計処理」です。
改めて本文を抜き出します。
(1) 資産は、原則として、取得価額で計上する。
(2) 負債のうち、債務は、原則として、債務額で計上する。
次に解説を抜き出します。
資産には、金銭債権、有価証券、棚卸資産、固定資産等が含まれますが、これらは原則として、(1)にあるように、取得価額、すなわち、資産を取得するために要した金額を基礎として、貸借対照表に計上します(一般に「取得原価主義」といいます。)。したがって、取得した後の時価の変動は、原則として、会計帳簿に反映されません。
なお、「取得価額」とは資産の取得又は製造のために要した金額のことをいい、例えば、購入品であれば、購入金額に付随費用を加えた金額をいいます。また、「取得原価」は取得価額を基礎として、適切に費用配分した後の金額のことをいい、例えば、棚卸資産であれば、総平均法等により費用配分した後の金額をいいます。
一方、負債には、金銭債務や引当金等が含まれますが、このうち債務については、(2)にあるように、債務を弁済するために将来支払うべき金額、すなわち債務額で貸借対照表に計上します。
現行の会計は取得原価主義会計といわれています。これは、解説にあるように資産の計上において取得原価を原則として計上し、その後の時価の変動を会計帳簿に反映されないという意味であり、時価で資産を計上する時価会計と対比されるものです。
では、今上場会社の会計基準は時価会計となっているのでしょうか?
そうではないと思います。あくまで取得原価主義会計の中で時価を適切に反映されているといえます。資産を単に資産を取得するために要した金額を基礎として計上するものというよりは、資産の意義を収益を獲得するのに有するものと考えているのです。その場合、収益を獲得する能力が取得原価以下になった場合は当然その価格、すなわち時価に洗い替えなければなりません。それが反映しているのが固定資産における減損会計でもあると思います。ただ、金融商品についてのみは市場があるものであり常に時価にさらされているため取得原価主義会計の枠外として時価主義がとられていると思います。
中小企業の会計としては、現行の上場会社の会計基準のながれではなく、あくまで伝統的な取得原価主義会計を採用しています。
すなわち、上場会社の会計基準と中小企業の会計基準はこの点においても考え方が異なっています。中小企業の会計基準を独自の会計基準としてとらえるべきとの考え方を反映した部分がこの「2.資産、負債の基本的な会計処理」であるともいえます。
改めて本文を抜き出します。
(1) 資産は、原則として、取得価額で計上する。
(2) 負債のうち、債務は、原則として、債務額で計上する。
次に解説を抜き出します。
資産には、金銭債権、有価証券、棚卸資産、固定資産等が含まれますが、これらは原則として、(1)にあるように、取得価額、すなわち、資産を取得するために要した金額を基礎として、貸借対照表に計上します(一般に「取得原価主義」といいます。)。したがって、取得した後の時価の変動は、原則として、会計帳簿に反映されません。
なお、「取得価額」とは資産の取得又は製造のために要した金額のことをいい、例えば、購入品であれば、購入金額に付随費用を加えた金額をいいます。また、「取得原価」は取得価額を基礎として、適切に費用配分した後の金額のことをいい、例えば、棚卸資産であれば、総平均法等により費用配分した後の金額をいいます。
一方、負債には、金銭債務や引当金等が含まれますが、このうち債務については、(2)にあるように、債務を弁済するために将来支払うべき金額、すなわち債務額で貸借対照表に計上します。
現行の会計は取得原価主義会計といわれています。これは、解説にあるように資産の計上において取得原価を原則として計上し、その後の時価の変動を会計帳簿に反映されないという意味であり、時価で資産を計上する時価会計と対比されるものです。
では、今上場会社の会計基準は時価会計となっているのでしょうか?
そうではないと思います。あくまで取得原価主義会計の中で時価を適切に反映されているといえます。資産を単に資産を取得するために要した金額を基礎として計上するものというよりは、資産の意義を収益を獲得するのに有するものと考えているのです。その場合、収益を獲得する能力が取得原価以下になった場合は当然その価格、すなわち時価に洗い替えなければなりません。それが反映しているのが固定資産における減損会計でもあると思います。ただ、金融商品についてのみは市場があるものであり常に時価にさらされているため取得原価主義会計の枠外として時価主義がとられていると思います。
中小企業の会計としては、現行の上場会社の会計基準のながれではなく、あくまで伝統的な取得原価主義会計を採用しています。
すなわち、上場会社の会計基準と中小企業の会計基準はこの点においても考え方が異なっています。中小企業の会計基準を独自の会計基準としてとらえるべきとの考え方を反映した部分がこの「2.資産、負債の基本的な会計処理」であるともいえます。
中小会計要領~各論その4
2014年07月24日
今日から「中小企業の会計に関する基本要領」の個別項目にはいっていきたいと思います。
まずは、「1. 収益、費用の基本的な会計処理」です。
改めて本文を抜き出します。
(1) 収益は、原則として、製品、商品の販売又はサービスの提供を行い、かつ、 これに対する現金及び預金、売掛金、受取手形等を取得した時に計上する。
(2) 費用は、原則として、費用の発生原因となる取引が発生した時又はサービスの提供を受けた時に計上する。
(3) 収益とこれに関連する費用は、両者を対応させて期間損益を計算する。
(4) 収益及び費用は、原則として、総額で計上し、収益の項目と費用の項目とを直接に相殺することによってその全部又は一部を損益計算書から除去してはならない。
次に解説を抜き出します。
企業の利益は、一定の会計期間における収益から費用を差し引いたものであり、収益と費用をどのように計上するかが重要となります。
ここで、収益と費用は、現金及び預金の受取り又は支払いに基づき計上するのではなく、その発生した期間に正しく割り当てられるように処理することが必要となります。
収益のうち、企業の主たる営業活動の成果を表す売上高は、(1)にあるように、製品、商品の販売又はサービスの提供を行い、かつ、これに対する対価(現金及び預金、売掛金、受取手形等)を受け取った時(売掛金の場合には、発生した時)に認識するのが原則的な考え方です(一般に「実現主義」といいます。)。実務上、製品や商品の販売の場合には、売上高は、製品や商品を出荷した時に計上する方法が多く見られますが、各々の企業の取引の実態に応じて、決定することとなります。
一方、費用については、(2)にあるように、現金及び預金の支払いではなく、費用の発生原因となる取引が発生した時又はサービスの提供を受けた時に認識するのが原則的な考え方です(一般に「発生主義」といいます。)。
ここで、適正な利益を計算するために、費用の計上は、(3)にあるように、一定の会計期間において計上した収益と対応させる考え方も必要となります。例えば、販売した製品や商品の売上原価は、売上高に対応させて費用として計上することが必要になります。
なお、(4)にあるように、収益と費用は原則として総額で計上する必要があります。例えば、賃借している建物を転貸する場合は、受取家賃と支払家賃の双方を計上することとなります。
ご覧いただいたように本文は要点をうまくまとめていますし、解説もわかりやすいように解説されています。
この中小企業会計要領を読んでいただくだけでも十分な会計入門になると思います。
要約すると、
利益=収益-費用で表されます。
収益は実現主義で認識し、費用は発生主義で認識します。
期間損益においては費用収益対応の原則が基本原則となります。
また、収益及び費用は原則として総額主義で計上することになります。
これを丁寧に解説しているのが中小企業会計要領の「1. 収益、費用の基本的な会計処理」ということになります。
まずは、「1. 収益、費用の基本的な会計処理」です。
改めて本文を抜き出します。
(1) 収益は、原則として、製品、商品の販売又はサービスの提供を行い、かつ、 これに対する現金及び預金、売掛金、受取手形等を取得した時に計上する。
(2) 費用は、原則として、費用の発生原因となる取引が発生した時又はサービスの提供を受けた時に計上する。
(3) 収益とこれに関連する費用は、両者を対応させて期間損益を計算する。
(4) 収益及び費用は、原則として、総額で計上し、収益の項目と費用の項目とを直接に相殺することによってその全部又は一部を損益計算書から除去してはならない。
次に解説を抜き出します。
企業の利益は、一定の会計期間における収益から費用を差し引いたものであり、収益と費用をどのように計上するかが重要となります。
ここで、収益と費用は、現金及び預金の受取り又は支払いに基づき計上するのではなく、その発生した期間に正しく割り当てられるように処理することが必要となります。
収益のうち、企業の主たる営業活動の成果を表す売上高は、(1)にあるように、製品、商品の販売又はサービスの提供を行い、かつ、これに対する対価(現金及び預金、売掛金、受取手形等)を受け取った時(売掛金の場合には、発生した時)に認識するのが原則的な考え方です(一般に「実現主義」といいます。)。実務上、製品や商品の販売の場合には、売上高は、製品や商品を出荷した時に計上する方法が多く見られますが、各々の企業の取引の実態に応じて、決定することとなります。
一方、費用については、(2)にあるように、現金及び預金の支払いではなく、費用の発生原因となる取引が発生した時又はサービスの提供を受けた時に認識するのが原則的な考え方です(一般に「発生主義」といいます。)。
ここで、適正な利益を計算するために、費用の計上は、(3)にあるように、一定の会計期間において計上した収益と対応させる考え方も必要となります。例えば、販売した製品や商品の売上原価は、売上高に対応させて費用として計上することが必要になります。
なお、(4)にあるように、収益と費用は原則として総額で計上する必要があります。例えば、賃借している建物を転貸する場合は、受取家賃と支払家賃の双方を計上することとなります。
ご覧いただいたように本文は要点をうまくまとめていますし、解説もわかりやすいように解説されています。
この中小企業会計要領を読んでいただくだけでも十分な会計入門になると思います。
要約すると、
利益=収益-費用で表されます。
収益は実現主義で認識し、費用は発生主義で認識します。
期間損益においては費用収益対応の原則が基本原則となります。
また、収益及び費用は原則として総額主義で計上することになります。
これを丁寧に解説しているのが中小企業会計要領の「1. 収益、費用の基本的な会計処理」ということになります。
中小会計要領~各論その3
2014年07月23日
今日は前回に引き続き中小会計要領の各論の本文を抜き出して記載します。
今日は、11.引当金からです。
11.引当金
(1) 以下に該当するものを引当金として、当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として計上し、当該引当金の残高を貸借対照表の負債の部又は資産の部に記載する。
・将来の特定の費用又は損失であること
・発生が当期以前の事象に起因すること
・発生の可能性が高いこと
・金額を合理的に見積ることができること
(2) 賞与引当金については、翌期に従業員に対して支給する賞与の見積額のうち、当期の負担に属する部分の金額を計上する。
(3) 退職給付引当金については、退職金規程や退職金等の支払いに関する合意があり、退職一時金制度を採用している場合において、当期末における退職給付に係る自己都合要支給額を基に計上する。
(4) 中小企業退職金共済、特定退職金共済、確定拠出年金等、将来の退職給付について拠出以後に追加的な負担が生じない制度を採用している場合においては、毎期の掛金を費用処理する。
12.外貨建取引等
(1) 外貨建取引(外国通貨建で受け払いされる取引)は、当該取引発生時の為替相場による円換算額で計上する。
(2) 外貨建金銭債権債務については、取得時の為替相場又は決算時の為替相場による円換算額で計上する。
13.純資産
(1) 純資産とは、資産の部の合計額から負債の部の合計額を控除した額をいう。
(2) 純資産のうち株主資本は、資本金、資本剰余金、利益剰余金等から構成される。
14. 注記
(1) 会社計算規則に基づき、重要な会計方針に係る事項、株主資本等変動計算書に関する事項等を注記する。
(2) 本要領に拠って計算書類を作成した場合には、その旨を記載する。
中小会計要領の各論の本文は以上です。
中小会計要領の各論の本文を今回を含め3回にわたって抜き出させていただきました。
今日は、11.引当金からです。
11.引当金
(1) 以下に該当するものを引当金として、当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として計上し、当該引当金の残高を貸借対照表の負債の部又は資産の部に記載する。
・将来の特定の費用又は損失であること
・発生が当期以前の事象に起因すること
・発生の可能性が高いこと
・金額を合理的に見積ることができること
(2) 賞与引当金については、翌期に従業員に対して支給する賞与の見積額のうち、当期の負担に属する部分の金額を計上する。
(3) 退職給付引当金については、退職金規程や退職金等の支払いに関する合意があり、退職一時金制度を採用している場合において、当期末における退職給付に係る自己都合要支給額を基に計上する。
(4) 中小企業退職金共済、特定退職金共済、確定拠出年金等、将来の退職給付について拠出以後に追加的な負担が生じない制度を採用している場合においては、毎期の掛金を費用処理する。
12.外貨建取引等
(1) 外貨建取引(外国通貨建で受け払いされる取引)は、当該取引発生時の為替相場による円換算額で計上する。
(2) 外貨建金銭債権債務については、取得時の為替相場又は決算時の為替相場による円換算額で計上する。
13.純資産
(1) 純資産とは、資産の部の合計額から負債の部の合計額を控除した額をいう。
(2) 純資産のうち株主資本は、資本金、資本剰余金、利益剰余金等から構成される。
14. 注記
(1) 会社計算規則に基づき、重要な会計方針に係る事項、株主資本等変動計算書に関する事項等を注記する。
(2) 本要領に拠って計算書類を作成した場合には、その旨を記載する。
中小会計要領の各論の本文は以上です。
中小会計要領の各論の本文を今回を含め3回にわたって抜き出させていただきました。
中小会計要領~各論その2
2014年07月22日
今日は前回に引き続き中小会計要領の各論の本文を抜き出して記載します。
今日は、6.棚卸資産から10.リース取引まで
6.棚卸資産
(1) 棚卸資産は、原則として、取得原価で計上する。
(2) 棚卸資産の評価基準は、原価法又は低価法による。
(3) 棚卸資産の評価方法は、個別法、先入先出法、総平均法、移動平均法、最終仕入原価法、売価還元法等による。
(4) 時価が取得原価よりも著しく下落したときは、回復の見込みがあると判断した場合を除き、評価損を計上する。
7.経過勘定
(1) 前払費用及び前受収益は、当期の損益計算に含めない。
(2) 未払費用及び未収収益は、当期の損益計算に反映する。
8.固定資産
(1) 固定資産は、有形固定資産(建物、機械装置、土地等)、無形固定資産(ソフトウェア、借地権、特許権、のれん等)及び投資その他の資産に分類する。
(2) 固定資産は、原則として、取得原価で計上する。
(3) 有形固定資産は、定率法、定額法等の方法に従い、相当の減価償却を行う。
(4) 無形固定資産は、原則として定額法により、相当の減価償却を行う。
(5) 固定資産の耐用年数は、法人税法に定める期間等、適切な利用期間とする。
(6) 固定資産について、災害等により著しい資産価値の下落が判明したときは、評価損を計上する。
9. 繰延資産
(1) 創立費、開業費、開発費、株式交付費、社債発行費及び新株予約権発行費は、費用処理するか、繰延資産として資産計上する。
(2) 繰延資産は、その効果の及ぶ期間にわたって償却する。
10.リース取引
リース取引に係る借手は、賃貸借取引又は売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。
11.引当金以降については次回記載いたします。
今日は、6.棚卸資産から10.リース取引まで
6.棚卸資産
(1) 棚卸資産は、原則として、取得原価で計上する。
(2) 棚卸資産の評価基準は、原価法又は低価法による。
(3) 棚卸資産の評価方法は、個別法、先入先出法、総平均法、移動平均法、最終仕入原価法、売価還元法等による。
(4) 時価が取得原価よりも著しく下落したときは、回復の見込みがあると判断した場合を除き、評価損を計上する。
7.経過勘定
(1) 前払費用及び前受収益は、当期の損益計算に含めない。
(2) 未払費用及び未収収益は、当期の損益計算に反映する。
8.固定資産
(1) 固定資産は、有形固定資産(建物、機械装置、土地等)、無形固定資産(ソフトウェア、借地権、特許権、のれん等)及び投資その他の資産に分類する。
(2) 固定資産は、原則として、取得原価で計上する。
(3) 有形固定資産は、定率法、定額法等の方法に従い、相当の減価償却を行う。
(4) 無形固定資産は、原則として定額法により、相当の減価償却を行う。
(5) 固定資産の耐用年数は、法人税法に定める期間等、適切な利用期間とする。
(6) 固定資産について、災害等により著しい資産価値の下落が判明したときは、評価損を計上する。
9. 繰延資産
(1) 創立費、開業費、開発費、株式交付費、社債発行費及び新株予約権発行費は、費用処理するか、繰延資産として資産計上する。
(2) 繰延資産は、その効果の及ぶ期間にわたって償却する。
10.リース取引
リース取引に係る借手は、賃貸借取引又は売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。
11.引当金以降については次回記載いたします。
中小会期要領~各論その1
2014年07月17日
今日は中小会計要領の各論の本文を抜き出して記載します。
今日は、1.収益、費用の基本的な会計処理から5.有価証券まで
Ⅱ 各論
1. 収益、費用の基本的な会計処理
(1) 収益は、原則として、製品、商品の販売又はサービスの提供を行い、かつ、 これに対する現金及び預金、売掛金、受取手形等を取得した時に計上する。
(2) 費用は、原則として、費用の発生原因となる取引が発生した時又はサービスの提供を受けた時に計上する。
(3) 収益とこれに関連する費用は、両者を対応させて期間損益を計算する。
(4) 収益及び費用は、原則として、総額で計上し、収益の項目と費用の項目とを直接に相殺することによってその全部又は一部を損益計算書から除去してはならない。
2.資産、負債の基本的な会計処理
(1) 資産は、原則として、取得価額で計上する。
(2) 負債のうち、債務は、原則として、債務額で計上する。
3.金銭債権及び金銭債務
(1) 金銭債権は、原則として、取得価額で計上する。
(2) 金銭債務は、原則として、債務額で計上する。
(3) 受取手形割引額及び受取手形裏書譲渡額は、貸借対照表の注記とする。
4.貸倒損失、貸倒引当金
(1) 倒産手続き等により債権が法的に消滅したときは、その金額を貸倒損失として計上する。
(2) 債務者の資産状況、支払能力等からみて回収不能な債権については、その回収不能額を貸倒損失として計上する。
(3) 債務者の資産状況、支払能力等からみて回収不能のおそれのある債権については、その回収不能見込額を貸倒引当金として計上する。
5. 有価証券
(1) 有価証券は、原則として、取得原価で計上する。
(2) 売買目的の有価証券を保有する場合は、時価で計上する。
(3) 有価証券の評価方法は、総平均法、移動平均法等による。
(4) 時価が取得原価よりも著しく下落したときは、回復の見込みがあると判断した場合を除き、評価損を計上する。
6.棚卸資産以降については次回記載いたします。
今日は、1.収益、費用の基本的な会計処理から5.有価証券まで
Ⅱ 各論
1. 収益、費用の基本的な会計処理
(1) 収益は、原則として、製品、商品の販売又はサービスの提供を行い、かつ、 これに対する現金及び預金、売掛金、受取手形等を取得した時に計上する。
(2) 費用は、原則として、費用の発生原因となる取引が発生した時又はサービスの提供を受けた時に計上する。
(3) 収益とこれに関連する費用は、両者を対応させて期間損益を計算する。
(4) 収益及び費用は、原則として、総額で計上し、収益の項目と費用の項目とを直接に相殺することによってその全部又は一部を損益計算書から除去してはならない。
2.資産、負債の基本的な会計処理
(1) 資産は、原則として、取得価額で計上する。
(2) 負債のうち、債務は、原則として、債務額で計上する。
3.金銭債権及び金銭債務
(1) 金銭債権は、原則として、取得価額で計上する。
(2) 金銭債務は、原則として、債務額で計上する。
(3) 受取手形割引額及び受取手形裏書譲渡額は、貸借対照表の注記とする。
4.貸倒損失、貸倒引当金
(1) 倒産手続き等により債権が法的に消滅したときは、その金額を貸倒損失として計上する。
(2) 債務者の資産状況、支払能力等からみて回収不能な債権については、その回収不能額を貸倒損失として計上する。
(3) 債務者の資産状況、支払能力等からみて回収不能のおそれのある債権については、その回収不能見込額を貸倒引当金として計上する。
5. 有価証券
(1) 有価証券は、原則として、取得原価で計上する。
(2) 売買目的の有価証券を保有する場合は、時価で計上する。
(3) 有価証券の評価方法は、総平均法、移動平均法等による。
(4) 時価が取得原価よりも著しく下落したときは、回復の見込みがあると判断した場合を除き、評価損を計上する。
6.棚卸資産以降については次回記載いたします。