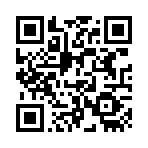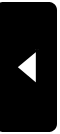貸借対照表について
2013年11月26日
おはようございます。
頭で分かっていても実践が伴わない。実践していく中で理解していく。
実務に出れば実践が第一という事になります。
しかし、実践が第一とはいいながらそのベースをしっかりと学んでいく必要もあると思います。
勉強しないから、専門家に任せる。専門家にはある程度任せる必要がありますが、専門家が説明する言葉の意味をしっかりと学んでいくことも必要であると思います。
税務や会計については、専門家に任せているばかりではなく、自分で理解をしておく人が必要ですね。経営計画は未来の予想ですが、そのための基礎となる会計は現在の事象をあらわすものです。それに、会計は経営者の行動を適切に反映するものであり、その行動の結果を取り繕うとすることは粉飾を行うということです。そして、その経営者の行動が知らないために行う場合において会社法違反や商法違反の行為となるケースも大いにあることです。また、税務上不利益を招くことも大いにあります。税務上のリスクがあるかどうかについては事前に顧問税理士に相談することも必要だと思います。
さて、今日は貸借対照表についてお話したいと思います。
中小企業においては、現在決算書は貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書の3つを指します。
貸借対照表はBalanceSeat(略してBS)というように、借方と貸方が一致していることが基本となります。一致するためには、複式簿記により記帳をしていくことが必要です。
昔は手書きで仕訳をきり、その仕訳を転記して試算表をつくり、決算整理仕訳をおこして、精算表をつくり、その後決算書を作成していきました。 今は会計ソフトを利用することがほとんどですので、こういった手作業の業務は必要なく、当初の仕訳を会計ソフトで入力するだけで、試算表も作成されますし、決算整理仕訳の入力により、決算書も作成されます。そのため、ベースとして、仕訳の基本を理解しておけば決算書まで作成することができます。決算書を読むための基本としてこういった流れを理解しておくことも求められてきます。
貸借対照表の話に戻りますが、借方には資産が計上されています。そして、貸方には、負債と純資産が計上されています。貸方は企業がどういう方法で資金を調達したかを表しているものであり、借方は企業が調達した資金をどういう方法で運用しているかをあらわしています。負債は他人資本、資本は自己資本といいますが、これは資金の調達をどういった方法で集めているかをあらわしていることからくる名称です。
資産及び負債については、1年以内に支払もしくは回収されるかどうかで区分することになります。この区分により、流動資産か固定資産、もしくは流動負債か固定負債に区分されます。ただし、営業目的の取引により生じた債権・債務、すなわち、売掛金・買掛金などは流動資産もしくは流動負債に属するものとします。また、資産の部においては、支払がすでに発生していますが、将来の収益に貢献するものとしていまだに費用化されていないものを繰延資産として計上することにしています。繰延資産は、株式交付費、社債発行費等(新株予約権発行費を含む)、創立費、開業費、開発費の5つの項目に限定されています。
純資産の部は、以前は資本の部といっていましたが、上場会社の会計基準において必ずしも株主資本といいきれないものが資本の部に計上されることになってきたため、名称も資本から純資産に変更されることになりました。ただし、中小企業においては、ほとんど株主資本に関するものしか計上されることがないため、株主資本しか、純資産の部では表示されないと思います。株主資本は、資本金、資本剰余金、利益剰余金にわかれます。
今日はここまで。
頭で分かっていても実践が伴わない。実践していく中で理解していく。
実務に出れば実践が第一という事になります。
しかし、実践が第一とはいいながらそのベースをしっかりと学んでいく必要もあると思います。
勉強しないから、専門家に任せる。専門家にはある程度任せる必要がありますが、専門家が説明する言葉の意味をしっかりと学んでいくことも必要であると思います。
税務や会計については、専門家に任せているばかりではなく、自分で理解をしておく人が必要ですね。経営計画は未来の予想ですが、そのための基礎となる会計は現在の事象をあらわすものです。それに、会計は経営者の行動を適切に反映するものであり、その行動の結果を取り繕うとすることは粉飾を行うということです。そして、その経営者の行動が知らないために行う場合において会社法違反や商法違反の行為となるケースも大いにあることです。また、税務上不利益を招くことも大いにあります。税務上のリスクがあるかどうかについては事前に顧問税理士に相談することも必要だと思います。
さて、今日は貸借対照表についてお話したいと思います。
中小企業においては、現在決算書は貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書の3つを指します。
貸借対照表はBalanceSeat(略してBS)というように、借方と貸方が一致していることが基本となります。一致するためには、複式簿記により記帳をしていくことが必要です。
昔は手書きで仕訳をきり、その仕訳を転記して試算表をつくり、決算整理仕訳をおこして、精算表をつくり、その後決算書を作成していきました。 今は会計ソフトを利用することがほとんどですので、こういった手作業の業務は必要なく、当初の仕訳を会計ソフトで入力するだけで、試算表も作成されますし、決算整理仕訳の入力により、決算書も作成されます。そのため、ベースとして、仕訳の基本を理解しておけば決算書まで作成することができます。決算書を読むための基本としてこういった流れを理解しておくことも求められてきます。
貸借対照表の話に戻りますが、借方には資産が計上されています。そして、貸方には、負債と純資産が計上されています。貸方は企業がどういう方法で資金を調達したかを表しているものであり、借方は企業が調達した資金をどういう方法で運用しているかをあらわしています。負債は他人資本、資本は自己資本といいますが、これは資金の調達をどういった方法で集めているかをあらわしていることからくる名称です。
資産及び負債については、1年以内に支払もしくは回収されるかどうかで区分することになります。この区分により、流動資産か固定資産、もしくは流動負債か固定負債に区分されます。ただし、営業目的の取引により生じた債権・債務、すなわち、売掛金・買掛金などは流動資産もしくは流動負債に属するものとします。また、資産の部においては、支払がすでに発生していますが、将来の収益に貢献するものとしていまだに費用化されていないものを繰延資産として計上することにしています。繰延資産は、株式交付費、社債発行費等(新株予約権発行費を含む)、創立費、開業費、開発費の5つの項目に限定されています。
純資産の部は、以前は資本の部といっていましたが、上場会社の会計基準において必ずしも株主資本といいきれないものが資本の部に計上されることになってきたため、名称も資本から純資産に変更されることになりました。ただし、中小企業においては、ほとんど株主資本に関するものしか計上されることがないため、株主資本しか、純資産の部では表示されないと思います。株主資本は、資本金、資本剰余金、利益剰余金にわかれます。
今日はここまで。
Posted by
山本公認会計士・税理士事務所
at
09:11
│Comments(
0
) │
会計
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。