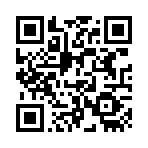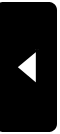中小会計要領~各論その5
2014年07月25日
今日は「中小企業の会計に関する基本要領」の「2.資産、負債の基本的な会計処理」です。
改めて本文を抜き出します。
(1) 資産は、原則として、取得価額で計上する。
(2) 負債のうち、債務は、原則として、債務額で計上する。
次に解説を抜き出します。
資産には、金銭債権、有価証券、棚卸資産、固定資産等が含まれますが、これらは原則として、(1)にあるように、取得価額、すなわち、資産を取得するために要した金額を基礎として、貸借対照表に計上します(一般に「取得原価主義」といいます。)。したがって、取得した後の時価の変動は、原則として、会計帳簿に反映されません。
なお、「取得価額」とは資産の取得又は製造のために要した金額のことをいい、例えば、購入品であれば、購入金額に付随費用を加えた金額をいいます。また、「取得原価」は取得価額を基礎として、適切に費用配分した後の金額のことをいい、例えば、棚卸資産であれば、総平均法等により費用配分した後の金額をいいます。
一方、負債には、金銭債務や引当金等が含まれますが、このうち債務については、(2)にあるように、債務を弁済するために将来支払うべき金額、すなわち債務額で貸借対照表に計上します。
現行の会計は取得原価主義会計といわれています。これは、解説にあるように資産の計上において取得原価を原則として計上し、その後の時価の変動を会計帳簿に反映されないという意味であり、時価で資産を計上する時価会計と対比されるものです。
では、今上場会社の会計基準は時価会計となっているのでしょうか?
そうではないと思います。あくまで取得原価主義会計の中で時価を適切に反映されているといえます。資産を単に資産を取得するために要した金額を基礎として計上するものというよりは、資産の意義を収益を獲得するのに有するものと考えているのです。その場合、収益を獲得する能力が取得原価以下になった場合は当然その価格、すなわち時価に洗い替えなければなりません。それが反映しているのが固定資産における減損会計でもあると思います。ただ、金融商品についてのみは市場があるものであり常に時価にさらされているため取得原価主義会計の枠外として時価主義がとられていると思います。
中小企業の会計としては、現行の上場会社の会計基準のながれではなく、あくまで伝統的な取得原価主義会計を採用しています。
すなわち、上場会社の会計基準と中小企業の会計基準はこの点においても考え方が異なっています。中小企業の会計基準を独自の会計基準としてとらえるべきとの考え方を反映した部分がこの「2.資産、負債の基本的な会計処理」であるともいえます。
改めて本文を抜き出します。
(1) 資産は、原則として、取得価額で計上する。
(2) 負債のうち、債務は、原則として、債務額で計上する。
次に解説を抜き出します。
資産には、金銭債権、有価証券、棚卸資産、固定資産等が含まれますが、これらは原則として、(1)にあるように、取得価額、すなわち、資産を取得するために要した金額を基礎として、貸借対照表に計上します(一般に「取得原価主義」といいます。)。したがって、取得した後の時価の変動は、原則として、会計帳簿に反映されません。
なお、「取得価額」とは資産の取得又は製造のために要した金額のことをいい、例えば、購入品であれば、購入金額に付随費用を加えた金額をいいます。また、「取得原価」は取得価額を基礎として、適切に費用配分した後の金額のことをいい、例えば、棚卸資産であれば、総平均法等により費用配分した後の金額をいいます。
一方、負債には、金銭債務や引当金等が含まれますが、このうち債務については、(2)にあるように、債務を弁済するために将来支払うべき金額、すなわち債務額で貸借対照表に計上します。
現行の会計は取得原価主義会計といわれています。これは、解説にあるように資産の計上において取得原価を原則として計上し、その後の時価の変動を会計帳簿に反映されないという意味であり、時価で資産を計上する時価会計と対比されるものです。
では、今上場会社の会計基準は時価会計となっているのでしょうか?
そうではないと思います。あくまで取得原価主義会計の中で時価を適切に反映されているといえます。資産を単に資産を取得するために要した金額を基礎として計上するものというよりは、資産の意義を収益を獲得するのに有するものと考えているのです。その場合、収益を獲得する能力が取得原価以下になった場合は当然その価格、すなわち時価に洗い替えなければなりません。それが反映しているのが固定資産における減損会計でもあると思います。ただ、金融商品についてのみは市場があるものであり常に時価にさらされているため取得原価主義会計の枠外として時価主義がとられていると思います。
中小企業の会計としては、現行の上場会社の会計基準のながれではなく、あくまで伝統的な取得原価主義会計を採用しています。
すなわち、上場会社の会計基準と中小企業の会計基準はこの点においても考え方が異なっています。中小企業の会計基準を独自の会計基準としてとらえるべきとの考え方を反映した部分がこの「2.資産、負債の基本的な会計処理」であるともいえます。
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。