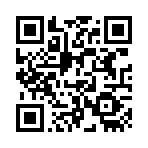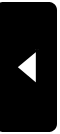中小会計要領~各論その4
2014年07月24日
今日から「中小企業の会計に関する基本要領」の個別項目にはいっていきたいと思います。
まずは、「1. 収益、費用の基本的な会計処理」です。
改めて本文を抜き出します。
(1) 収益は、原則として、製品、商品の販売又はサービスの提供を行い、かつ、 これに対する現金及び預金、売掛金、受取手形等を取得した時に計上する。
(2) 費用は、原則として、費用の発生原因となる取引が発生した時又はサービスの提供を受けた時に計上する。
(3) 収益とこれに関連する費用は、両者を対応させて期間損益を計算する。
(4) 収益及び費用は、原則として、総額で計上し、収益の項目と費用の項目とを直接に相殺することによってその全部又は一部を損益計算書から除去してはならない。
次に解説を抜き出します。
企業の利益は、一定の会計期間における収益から費用を差し引いたものであり、収益と費用をどのように計上するかが重要となります。
ここで、収益と費用は、現金及び預金の受取り又は支払いに基づき計上するのではなく、その発生した期間に正しく割り当てられるように処理することが必要となります。
収益のうち、企業の主たる営業活動の成果を表す売上高は、(1)にあるように、製品、商品の販売又はサービスの提供を行い、かつ、これに対する対価(現金及び預金、売掛金、受取手形等)を受け取った時(売掛金の場合には、発生した時)に認識するのが原則的な考え方です(一般に「実現主義」といいます。)。実務上、製品や商品の販売の場合には、売上高は、製品や商品を出荷した時に計上する方法が多く見られますが、各々の企業の取引の実態に応じて、決定することとなります。
一方、費用については、(2)にあるように、現金及び預金の支払いではなく、費用の発生原因となる取引が発生した時又はサービスの提供を受けた時に認識するのが原則的な考え方です(一般に「発生主義」といいます。)。
ここで、適正な利益を計算するために、費用の計上は、(3)にあるように、一定の会計期間において計上した収益と対応させる考え方も必要となります。例えば、販売した製品や商品の売上原価は、売上高に対応させて費用として計上することが必要になります。
なお、(4)にあるように、収益と費用は原則として総額で計上する必要があります。例えば、賃借している建物を転貸する場合は、受取家賃と支払家賃の双方を計上することとなります。
ご覧いただいたように本文は要点をうまくまとめていますし、解説もわかりやすいように解説されています。
この中小企業会計要領を読んでいただくだけでも十分な会計入門になると思います。
要約すると、
利益=収益-費用で表されます。
収益は実現主義で認識し、費用は発生主義で認識します。
期間損益においては費用収益対応の原則が基本原則となります。
また、収益及び費用は原則として総額主義で計上することになります。
これを丁寧に解説しているのが中小企業会計要領の「1. 収益、費用の基本的な会計処理」ということになります。
まずは、「1. 収益、費用の基本的な会計処理」です。
改めて本文を抜き出します。
(1) 収益は、原則として、製品、商品の販売又はサービスの提供を行い、かつ、 これに対する現金及び預金、売掛金、受取手形等を取得した時に計上する。
(2) 費用は、原則として、費用の発生原因となる取引が発生した時又はサービスの提供を受けた時に計上する。
(3) 収益とこれに関連する費用は、両者を対応させて期間損益を計算する。
(4) 収益及び費用は、原則として、総額で計上し、収益の項目と費用の項目とを直接に相殺することによってその全部又は一部を損益計算書から除去してはならない。
次に解説を抜き出します。
企業の利益は、一定の会計期間における収益から費用を差し引いたものであり、収益と費用をどのように計上するかが重要となります。
ここで、収益と費用は、現金及び預金の受取り又は支払いに基づき計上するのではなく、その発生した期間に正しく割り当てられるように処理することが必要となります。
収益のうち、企業の主たる営業活動の成果を表す売上高は、(1)にあるように、製品、商品の販売又はサービスの提供を行い、かつ、これに対する対価(現金及び預金、売掛金、受取手形等)を受け取った時(売掛金の場合には、発生した時)に認識するのが原則的な考え方です(一般に「実現主義」といいます。)。実務上、製品や商品の販売の場合には、売上高は、製品や商品を出荷した時に計上する方法が多く見られますが、各々の企業の取引の実態に応じて、決定することとなります。
一方、費用については、(2)にあるように、現金及び預金の支払いではなく、費用の発生原因となる取引が発生した時又はサービスの提供を受けた時に認識するのが原則的な考え方です(一般に「発生主義」といいます。)。
ここで、適正な利益を計算するために、費用の計上は、(3)にあるように、一定の会計期間において計上した収益と対応させる考え方も必要となります。例えば、販売した製品や商品の売上原価は、売上高に対応させて費用として計上することが必要になります。
なお、(4)にあるように、収益と費用は原則として総額で計上する必要があります。例えば、賃借している建物を転貸する場合は、受取家賃と支払家賃の双方を計上することとなります。
ご覧いただいたように本文は要点をうまくまとめていますし、解説もわかりやすいように解説されています。
この中小企業会計要領を読んでいただくだけでも十分な会計入門になると思います。
要約すると、
利益=収益-費用で表されます。
収益は実現主義で認識し、費用は発生主義で認識します。
期間損益においては費用収益対応の原則が基本原則となります。
また、収益及び費用は原則として総額主義で計上することになります。
これを丁寧に解説しているのが中小企業会計要領の「1. 収益、費用の基本的な会計処理」ということになります。
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。