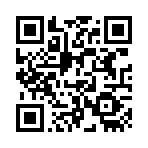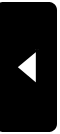4月1日から一部の印紙税が引き下げられます
2014年02月05日
おはようございます。
近江八幡は朝から雪です。朝起きた時点ではうっすらとした雪景色でしたが、こんこんと降る続きブログを書いている段階ではしっかりとした冬景色になっています。
先日知人の経営者から今年の4月から印紙税が引き下げられるのは知らなかったとの話を聞きました。
どうしても消費税の増税のほうに目を奪われがちですが、4月1日からは一部の印紙税が引き下げられます。
印紙税の引き下げの改正は平成25年度税制改正により改正され施行が平成26年4月1日となっています。すなわち、平成26年4月1日以降に作成される領収書等の非課税範囲が拡大されるほか、「不動産譲渡契約書」「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置が延長・拡充され、印紙税額も引き下げられます。
第一に、領収書等の「金銭又は有価証券の受取書」の印紙税額が現在、記載金額が3万円未満までが非課税のところ、平成26年4月1日から記載金額が5万円未満まで非課税となり、非課税範囲が拡大されます。なお、記載金額が5万円以上の印紙税額は従来どおりです。
第二に、「不動産譲渡契約書」「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置が延長・拡充され、印紙税額も引き下げられます。これまでは契約金額が1,000万円を超える「不動産譲渡契約書」「建設工事契約書」については、印紙税の軽減措置が適用されていましたが、その措置が延長拡充され、平成26年4月1日以降作成される「不動産譲渡契約書」は10万円超から、「建設工事請負契約書」は100万円超から軽減措置が適用され、印紙税額も引き下げられます。
近江八幡は朝から雪です。朝起きた時点ではうっすらとした雪景色でしたが、こんこんと降る続きブログを書いている段階ではしっかりとした冬景色になっています。
先日知人の経営者から今年の4月から印紙税が引き下げられるのは知らなかったとの話を聞きました。
どうしても消費税の増税のほうに目を奪われがちですが、4月1日からは一部の印紙税が引き下げられます。
印紙税の引き下げの改正は平成25年度税制改正により改正され施行が平成26年4月1日となっています。すなわち、平成26年4月1日以降に作成される領収書等の非課税範囲が拡大されるほか、「不動産譲渡契約書」「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置が延長・拡充され、印紙税額も引き下げられます。
第一に、領収書等の「金銭又は有価証券の受取書」の印紙税額が現在、記載金額が3万円未満までが非課税のところ、平成26年4月1日から記載金額が5万円未満まで非課税となり、非課税範囲が拡大されます。なお、記載金額が5万円以上の印紙税額は従来どおりです。
第二に、「不動産譲渡契約書」「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置が延長・拡充され、印紙税額も引き下げられます。これまでは契約金額が1,000万円を超える「不動産譲渡契約書」「建設工事契約書」については、印紙税の軽減措置が適用されていましたが、その措置が延長拡充され、平成26年4月1日以降作成される「不動産譲渡契約書」は10万円超から、「建設工事請負契約書」は100万円超から軽減措置が適用され、印紙税額も引き下げられます。
会計と税務は違います。
2014年01月31日
昨日まで変動損益計算書の話をしてきましたが、今日は全く違う話を投稿させて頂きます。
会計と財務は一緒ではなく、違います。
また、税務と会計も多くの部分で同じですが必ずしも同じではなく違います。
会計においても制度会計と管理会計では異なってくる部分が多いです。
では、財務と会計の違い、税務と会計の違い、制度会計と管理会計の違いをしっかりとわかっている経営者ってどのくらいいるのでしょうか?
違いがあるということがわかっていても、実際に違うということをしっかりと認識されていないのではないのかと思っています。
今日は税務と会計の違いについて述べていきたいと思います。
会計の利益は利益=収益-費用で計算されます。
税務の所得(会計でいうところの利益)は所得=益金-損金で計算されます。
収益=益金、費用=損金であれば何ら問題ありませんが、収益≠益金、費用≠損金であることがあり得ますので、所得の計算も利益の計算とは別途必要になります。
ただし、税務上の計算をイチからするのは大変であろうということで日本の法人税における所得の計算は会計上の利益の計算をスタートとして税務調整を行って所得の計算を行うことになります。
すなわち、所得=利益+加算-減算の計算が成り立つわけです。
ここに、加算には、収益ではないけれども益金ではある項目、すなわち益金算入の項目や費用ではあるが損金には算入されない項目、すなわち損金不算入の項目があります。具体的には、益金算入の項目には圧縮積立金取崩額があります。損金不算入項目は多々ありますが、例えば減価償却費の償却限度超過額の金額や賞与引当金の金額などがあります。
減算項目としては、収益ではありますが益金ではない項目、すなわち益金不算入の項目や費用ではありませんが、損金には算入さる項目、すなわち損金算入の項目があります。具体的には、益金不算入の項目には受取配当金の一部が該当します。また、損金算入の項目には欠損金の繰越控除額などが該当します。
税務と会計の違いをしっかい認識できてないと、会計上は費用として処理すべきなのに税務上損金として処理できないから費用計上もしたくないとの話が出てくるのです。
会計は自社の経営状況や財政状態を把握し、中小企業にとっては最大の債務者である金融機関に説明するために必要となる決算書を作成するために必要です。 一方、税務会計はあくまで法人税の申告のために必要であり、税務の処理の判断に会計が縛られるのはおかしいことなのですが、現実には税務上認められていないからとか税務上損金計上する必要ないからといって費用計上されていないケースが多々見られます。
やはり税務は税務、会計は会計としてその際をしっかり認識していくべきではないのでしょうか?
なお、会計と税務の差異は法人税の申告書の別表四にて調整計算がなされていますので、調整を見るには別表四をしっかりと読み解く必要があると思います。
会計と財務は一緒ではなく、違います。
また、税務と会計も多くの部分で同じですが必ずしも同じではなく違います。
会計においても制度会計と管理会計では異なってくる部分が多いです。
では、財務と会計の違い、税務と会計の違い、制度会計と管理会計の違いをしっかりとわかっている経営者ってどのくらいいるのでしょうか?
違いがあるということがわかっていても、実際に違うということをしっかりと認識されていないのではないのかと思っています。
今日は税務と会計の違いについて述べていきたいと思います。
会計の利益は利益=収益-費用で計算されます。
税務の所得(会計でいうところの利益)は所得=益金-損金で計算されます。
収益=益金、費用=損金であれば何ら問題ありませんが、収益≠益金、費用≠損金であることがあり得ますので、所得の計算も利益の計算とは別途必要になります。
ただし、税務上の計算をイチからするのは大変であろうということで日本の法人税における所得の計算は会計上の利益の計算をスタートとして税務調整を行って所得の計算を行うことになります。
すなわち、所得=利益+加算-減算の計算が成り立つわけです。
ここに、加算には、収益ではないけれども益金ではある項目、すなわち益金算入の項目や費用ではあるが損金には算入されない項目、すなわち損金不算入の項目があります。具体的には、益金算入の項目には圧縮積立金取崩額があります。損金不算入項目は多々ありますが、例えば減価償却費の償却限度超過額の金額や賞与引当金の金額などがあります。
減算項目としては、収益ではありますが益金ではない項目、すなわち益金不算入の項目や費用ではありませんが、損金には算入さる項目、すなわち損金算入の項目があります。具体的には、益金不算入の項目には受取配当金の一部が該当します。また、損金算入の項目には欠損金の繰越控除額などが該当します。
税務と会計の違いをしっかい認識できてないと、会計上は費用として処理すべきなのに税務上損金として処理できないから費用計上もしたくないとの話が出てくるのです。
会計は自社の経営状況や財政状態を把握し、中小企業にとっては最大の債務者である金融機関に説明するために必要となる決算書を作成するために必要です。 一方、税務会計はあくまで法人税の申告のために必要であり、税務の処理の判断に会計が縛られるのはおかしいことなのですが、現実には税務上認められていないからとか税務上損金計上する必要ないからといって費用計上されていないケースが多々見られます。
やはり税務は税務、会計は会計としてその際をしっかり認識していくべきではないのでしょうか?
なお、会計と税務の差異は法人税の申告書の別表四にて調整計算がなされていますので、調整を見るには別表四をしっかりと読み解く必要があると思います。
平成26年度税制改正大綱
2013年12月13日
昨日自民党から平成26年度税制改正大綱が出されました。
126ページにわたる税制改正大綱です。
特定の業種にかかる改正も含みますので、広く一般に関する改正というのは少ないのかもしれません。
とりあえず項目だけを抜き出して記載しておきます。
第一 平成26年度税制改正の基本的考え方
1 デフレ脱却・日本経済再生に向けた税制措置
(1)復興特別法人税の1年前倒し廃止
(2)民間投資と消費の拡大
(3)地域経済の活性化
(4)国家戦略特区
2 税制抜本改革の着実な実施
(1)車体課税の見直し
(2)地方法人課税の偏在是正
(3)給与所得控除の見直し
(4)軽減税率
3 復興支援のための税制上の措置
4 円滑・適正な納税のための環境整備
第二 平成26年度税制改正の具体的内容
Ⅰ 秋の大綱(民間投資活性化等のための税制改正大綱)での決定事項
一 民間投資の活性化
二 中小企業対策
三 民間企業等によるベンチャー投資等の促進
四 収益力の飛躍的な向上に向けた経営改革の促進
五 設備投資につながる制度・規制面での環境整備への対応
六 所得の拡大
Ⅱ 年末での決定事項
一 個人所得課税
1 給与所得控除の見直し
2 金融・証券税制
3 土地・住宅税制
4 租税特別措置等
5 その他
二 資産課税
1 復興支援のための税制上の措置
2 租税特別措置等
3 その他
三 法人課税
1 復興特別法人税の1年前倒し廃止
2 民間投資と消費の拡大
3 地域経済の活性化
4 国家戦略特区
5 地方法人課税の偏在是正
6 復興支援のための税制上の措置
7 沖縄振興関連
8 その他の租税特別措置等
9 その他
四 消費課税
1 車体課税の見直し
2 復興支援のための税制上の措置
3 租税特別措置等
4 その他
五 国際課税
1 国際課税原則の見直し(総合主義から帰属主義への変更)
六 納税環境整備
1 猶予制度の見直し
2 税理士制度の見直し
3 国税不服申立制度の見直し
4 その他
七 関税
1 暫定税率等の適用期限の延長
2 暫定的減免税制度の適用期限の延長
3 減免税制度の対象拡充
4 通関手続の迅速化等
5 その他
第三 検討事項
126ページにわたる税制改正大綱です。
特定の業種にかかる改正も含みますので、広く一般に関する改正というのは少ないのかもしれません。
とりあえず項目だけを抜き出して記載しておきます。
第一 平成26年度税制改正の基本的考え方
1 デフレ脱却・日本経済再生に向けた税制措置
(1)復興特別法人税の1年前倒し廃止
(2)民間投資と消費の拡大
(3)地域経済の活性化
(4)国家戦略特区
2 税制抜本改革の着実な実施
(1)車体課税の見直し
(2)地方法人課税の偏在是正
(3)給与所得控除の見直し
(4)軽減税率
3 復興支援のための税制上の措置
4 円滑・適正な納税のための環境整備
第二 平成26年度税制改正の具体的内容
Ⅰ 秋の大綱(民間投資活性化等のための税制改正大綱)での決定事項
一 民間投資の活性化
二 中小企業対策
三 民間企業等によるベンチャー投資等の促進
四 収益力の飛躍的な向上に向けた経営改革の促進
五 設備投資につながる制度・規制面での環境整備への対応
六 所得の拡大
Ⅱ 年末での決定事項
一 個人所得課税
1 給与所得控除の見直し
2 金融・証券税制
3 土地・住宅税制
4 租税特別措置等
5 その他
二 資産課税
1 復興支援のための税制上の措置
2 租税特別措置等
3 その他
三 法人課税
1 復興特別法人税の1年前倒し廃止
2 民間投資と消費の拡大
3 地域経済の活性化
4 国家戦略特区
5 地方法人課税の偏在是正
6 復興支援のための税制上の措置
7 沖縄振興関連
8 その他の租税特別措置等
9 その他
四 消費課税
1 車体課税の見直し
2 復興支援のための税制上の措置
3 租税特別措置等
4 その他
五 国際課税
1 国際課税原則の見直し(総合主義から帰属主義への変更)
六 納税環境整備
1 猶予制度の見直し
2 税理士制度の見直し
3 国税不服申立制度の見直し
4 その他
七 関税
1 暫定税率等の適用期限の延長
2 暫定的減免税制度の適用期限の延長
3 減免税制度の対象拡充
4 通関手続の迅速化等
5 その他
第三 検討事項
おはようございます。
2013年11月12日
おはようございます。
1ヶ月半前ぐらいまではこれが残暑かというくらい暑かったんですが、もう冬の寒さを感じているこの頃です。
特に今日はまた昨日よりも一段と冷え込んできていますね。
滋賀では寒さの訪れを感じているだけですが、北海道や東北ではもう雪も降っているようです。
法人の決算において、税務の決算書と会計の決算書は本来違います。
しかしながら、日本においては確定決算主義がとられています。
すなわち、会社の株主総会で承認された決算書に基づいて税務調整を行い、法人税の申告書を作成するということになっています。
中小企業においては、実際に株主総会を開いているところは少ないのかもしれませんが、形式的にも開いたことにし、監査役を設置している会社においては監査役による監査を受けた決算書の承認を株主総会で行うという事になっています。
仮に、会計における決算書と税務の決算書が同じであるならば、税務調整は必要ありません。
しかしながら、やはり異なるからこそ税務調整がなされるのです。
法人税の申告書で、税務調整をまとめた表が別表四にあたります。
当期の申告書でどのような調整がなされているのかを見ようとすれば、別表四を見ればだいたいわかります。
そして、今までの税務調整の累計を示しているのが別表五(2)ということがいえます。
法人税の申告書もそれぞれの別表がどこの別表と数字がつながっているのか、また、法人税の別表の数字が決算書のどの数字とつながっているのかということを考えながら見ていくと、意外な発見をするのかもしれませんね。
1ヶ月半前ぐらいまではこれが残暑かというくらい暑かったんですが、もう冬の寒さを感じているこの頃です。
特に今日はまた昨日よりも一段と冷え込んできていますね。
滋賀では寒さの訪れを感じているだけですが、北海道や東北ではもう雪も降っているようです。
法人の決算において、税務の決算書と会計の決算書は本来違います。
しかしながら、日本においては確定決算主義がとられています。
すなわち、会社の株主総会で承認された決算書に基づいて税務調整を行い、法人税の申告書を作成するということになっています。
中小企業においては、実際に株主総会を開いているところは少ないのかもしれませんが、形式的にも開いたことにし、監査役を設置している会社においては監査役による監査を受けた決算書の承認を株主総会で行うという事になっています。
仮に、会計における決算書と税務の決算書が同じであるならば、税務調整は必要ありません。
しかしながら、やはり異なるからこそ税務調整がなされるのです。
法人税の申告書で、税務調整をまとめた表が別表四にあたります。
当期の申告書でどのような調整がなされているのかを見ようとすれば、別表四を見ればだいたいわかります。
そして、今までの税務調整の累計を示しているのが別表五(2)ということがいえます。
法人税の申告書もそれぞれの別表がどこの別表と数字がつながっているのか、また、法人税の別表の数字が決算書のどの数字とつながっているのかということを考えながら見ていくと、意外な発見をするのかもしれませんね。
決算期
2013年05月15日
日本だと学校が3月卒業になるため、4月入社となります。
そのためか、多くの会社も3月決算が多くなります。
しかし、法人においては決算期は自由に決めれるため、多くの会社が3月末を決算期にしていることが多いようです。
中小企業においては、3月末以外の決算期も多いようです。
中には、税理士さんの都合で3月末決算や12月末決算から違う決算期に変えた会社もあるようです。
ただ、決算期を途中で変えた場合、その変更期は1年未満であるため、年度推移がとれないことにより、年度比較ができないという欠点があります。
個人においては、決算期は12月末と税務上で決まっています。
そして、そのための申告書を税務署に出す行為が確定申告です。
法人の場合は、原則として2ヶ月以内に税務署に法人税の申告並びに消費税の申告をする必要があります。
法人税の申告書に添付する決算書は、株主総会における承認をえる必要があるため、5月に株主総会を開催する必要があります。
中小企業でどれだけの会社が株主総会を開催しているのでしょうか?
上場会社において、株主総会を開催するためには、2週間前に株主総会通知を出す必要があります。
2ヶ月以内に株主総会を開催する為には、たとえば、3月決算だと5月の中旬には決算を固め、総会通知を出さないといけなくなります。
決算は固められるかもしれませんが、外部監査並びに内部監査を受けることを考えると日程的にきつくなります。
そこで、3ヶ月以内に株主総会を開催することになります。
税務上は、法人税の申告書は申告期限の延長の特例の申請をすることで、2ヶ月以内の申告書の提出を1ヶ月先の3ヶ月以内の提出にすることが可能です。ただし、消費税の申告書については、延長との特例の申請制度はありませんので、2ヶ月以内に申告書を提出する必要があります。このことにより、決算は実質的には2ヶ月以内に固めないといけないことになります。ただ、上場会社等においては株主総会による決算書の承認が得ていることが出来ないため、2ヶ月以内では法人税の申告書ができないだけです。
そのためか、多くの会社も3月決算が多くなります。
しかし、法人においては決算期は自由に決めれるため、多くの会社が3月末を決算期にしていることが多いようです。
中小企業においては、3月末以外の決算期も多いようです。
中には、税理士さんの都合で3月末決算や12月末決算から違う決算期に変えた会社もあるようです。
ただ、決算期を途中で変えた場合、その変更期は1年未満であるため、年度推移がとれないことにより、年度比較ができないという欠点があります。
個人においては、決算期は12月末と税務上で決まっています。
そして、そのための申告書を税務署に出す行為が確定申告です。
法人の場合は、原則として2ヶ月以内に税務署に法人税の申告並びに消費税の申告をする必要があります。
法人税の申告書に添付する決算書は、株主総会における承認をえる必要があるため、5月に株主総会を開催する必要があります。
中小企業でどれだけの会社が株主総会を開催しているのでしょうか?
上場会社において、株主総会を開催するためには、2週間前に株主総会通知を出す必要があります。
2ヶ月以内に株主総会を開催する為には、たとえば、3月決算だと5月の中旬には決算を固め、総会通知を出さないといけなくなります。
決算は固められるかもしれませんが、外部監査並びに内部監査を受けることを考えると日程的にきつくなります。
そこで、3ヶ月以内に株主総会を開催することになります。
税務上は、法人税の申告書は申告期限の延長の特例の申請をすることで、2ヶ月以内の申告書の提出を1ヶ月先の3ヶ月以内の提出にすることが可能です。ただし、消費税の申告書については、延長との特例の申請制度はありませんので、2ヶ月以内に申告書を提出する必要があります。このことにより、決算は実質的には2ヶ月以内に固めないといけないことになります。ただ、上場会社等においては株主総会による決算書の承認が得ていることが出来ないため、2ヶ月以内では法人税の申告書ができないだけです。