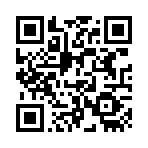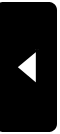中小会計要領の「各論」について
2014年07月16日
今日は、「中小企業の会計に関する基本要領」の各論にはいっていきたいと思います。
「中小企業の会計に関する基本要領」(以下、「中小会計要領」)の各論は以下の項目から成り立っています。
1. 収益、費用の基本的な会計処理
2. 資産、負債の基本的な会計処理
3. 金銭債権及び金銭債務
4. 貸倒損失、貸倒引当金
5. 有価証券
6. 棚卸資産
7. 経過勘定
8. 固定資産
9. 繰延資産
10.リース取引
11.引当金
12.外貨建取引等
13.純資産
14.注記
一方、「中小企業の会計に関する指針」(以下、「中小企業会計指針」)の各論は以下の項目から成り立っています。
金銭債権
貸倒損失・貸倒引当金
有価証券
棚卸資産
経過勘定等
固定資産
繰延資産
金銭債務
引当金
退職給付債務・退職給付引当金
税金費用・税金債務
税効果会計
純資産
収益・費用の計上
リース取引
外貨建取引等
組織再編の会計(企業結合会計及び事業分離会計)
個別注記表
決算公告と貸借対照表及び損益計算書並びに株主資本等変動計算書の例示
今後の検討事項
中小企業会計指針において取り上げられていて中小会計要領に取り上げられていない項目としては、税効果会計、組織再編の会計等があります。
「中小企業の会計に関する基本要領」(以下、「中小会計要領」)の各論は以下の項目から成り立っています。
1. 収益、費用の基本的な会計処理
2. 資産、負債の基本的な会計処理
3. 金銭債権及び金銭債務
4. 貸倒損失、貸倒引当金
5. 有価証券
6. 棚卸資産
7. 経過勘定
8. 固定資産
9. 繰延資産
10.リース取引
11.引当金
12.外貨建取引等
13.純資産
14.注記
一方、「中小企業の会計に関する指針」(以下、「中小企業会計指針」)の各論は以下の項目から成り立っています。
金銭債権
貸倒損失・貸倒引当金
有価証券
棚卸資産
経過勘定等
固定資産
繰延資産
金銭債務
引当金
退職給付債務・退職給付引当金
税金費用・税金債務
税効果会計
純資産
収益・費用の計上
リース取引
外貨建取引等
組織再編の会計(企業結合会計及び事業分離会計)
個別注記表
決算公告と貸借対照表及び損益計算書並びに株主資本等変動計算書の例示
今後の検討事項
中小企業会計指針において取り上げられていて中小会計要領に取り上げられていない項目としては、税効果会計、組織再編の会計等があります。
中小企業の会計に関する基本要領 総論その2
2014年07月11日
今日は、昨日に引き続き「中小企業の会計に関する基本要領」の総論について述べていきたいと思います。
「中小企業の会計に関する基本要領」(以下、「中小会計要領」)の総論は以下の項目から成り立っています。
1.目的
2.本要領の利用が想定される会社
3.企業会計基準、中小指針の利用
4.複数ある会計処理方法の取扱い
5.各論で示していない会計処理等の取扱い
6.国際会計基準との関係
7.本要領の改訂
8.記帳の重要性
9.本要領の利用上の留意事項
中小会計要領の総論の 4.複数ある会計処理方法の取扱い、8.記帳の重要性、9.本要領の利用上の留意事項において「企業会計原則」における一般原則にあたるものが示されている。
4. 複数ある会計処理方法の取扱い
(1) 本要領により複数の会計処理の方法が認められている場合には、企業の実態等に応じて、適切な会計処理の方法を選択して適用する。
(2) 会計処理の方法は、毎期継続して同じ方法を適用する必要があり、これを変更するに当たっては、合理的な理由を必要とし、変更した旨、その理由及び影響の内容を注記する。
8. 記帳の重要性
本要領の利用にあたっては、適切な記帳が前提とされている。経営者が自社の経営状況を適切に把握するために記帳が重要である。記帳は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って行い、適時に、整然かつ明瞭に、正確かつ網羅的に会計帳簿を作成しなければならない。
9. 本要領の利用上の留意事項
本要領の利用にあたっては、上記1.~8.とともに以下の考え方にも留意する必要がある。
① 企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するもので なければならない。(真実性の原則)
② 資本取引と損益取引は明瞭に区別しなければならない。(資本取引と損益取引の区分の原則)
③ 企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。(明瞭性の原則)
④ 企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない。(保守主義の原則)
⑤ 株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。(単一性の原則)
⑥ 企業会計の目的は、企業の財務内容を明らかにし、企業の経営状況に関する利害関係者の判断を誤らせないようにすることにある。このため、重要性の乏しいものについては、本来の会計処理によらないで、他の簡便な方法により処理することも認められる。(重要性の原則)
「4.複数ある会計処理方法の取扱い」は、いわゆる継続性の原則をのべたものである。また、「8. 記帳の重要性」は、正規の簿記の原則をのべたものであるが、中小企業において適時に記帳することが出来ていないこともあり、記帳の重要性として独立してのべたものであろう。
「中小企業の会計に関する基本要領」(以下、「中小会計要領」)の総論は以下の項目から成り立っています。
1.目的
2.本要領の利用が想定される会社
3.企業会計基準、中小指針の利用
4.複数ある会計処理方法の取扱い
5.各論で示していない会計処理等の取扱い
6.国際会計基準との関係
7.本要領の改訂
8.記帳の重要性
9.本要領の利用上の留意事項
中小会計要領の総論の 4.複数ある会計処理方法の取扱い、8.記帳の重要性、9.本要領の利用上の留意事項において「企業会計原則」における一般原則にあたるものが示されている。
4. 複数ある会計処理方法の取扱い
(1) 本要領により複数の会計処理の方法が認められている場合には、企業の実態等に応じて、適切な会計処理の方法を選択して適用する。
(2) 会計処理の方法は、毎期継続して同じ方法を適用する必要があり、これを変更するに当たっては、合理的な理由を必要とし、変更した旨、その理由及び影響の内容を注記する。
8. 記帳の重要性
本要領の利用にあたっては、適切な記帳が前提とされている。経営者が自社の経営状況を適切に把握するために記帳が重要である。記帳は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って行い、適時に、整然かつ明瞭に、正確かつ網羅的に会計帳簿を作成しなければならない。
9. 本要領の利用上の留意事項
本要領の利用にあたっては、上記1.~8.とともに以下の考え方にも留意する必要がある。
① 企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するもので なければならない。(真実性の原則)
② 資本取引と損益取引は明瞭に区別しなければならない。(資本取引と損益取引の区分の原則)
③ 企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。(明瞭性の原則)
④ 企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない。(保守主義の原則)
⑤ 株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。(単一性の原則)
⑥ 企業会計の目的は、企業の財務内容を明らかにし、企業の経営状況に関する利害関係者の判断を誤らせないようにすることにある。このため、重要性の乏しいものについては、本来の会計処理によらないで、他の簡便な方法により処理することも認められる。(重要性の原則)
「4.複数ある会計処理方法の取扱い」は、いわゆる継続性の原則をのべたものである。また、「8. 記帳の重要性」は、正規の簿記の原則をのべたものであるが、中小企業において適時に記帳することが出来ていないこともあり、記帳の重要性として独立してのべたものであろう。
中小会計要領~総論その1
2014年07月10日
今日は、「中小企業の会計に関する基本要領」の総論について述べていきたいと思います。
中小企業の会計に関するルールは現行2つの会計に関するルールが出されている。一つは「中小企業の会計に関する指針」(以下、中小指針)、もう一つは「中小企業の会計に関する基本要領」(以下、会計要領)である。
中小指針は、上場企業が適用している会計基準の簡易版となっているため、会計基準の変更に伴い中小指針も変更されることになる。そのため、中小指針は公表されていこう毎年変更されている。
一方、会計要領は計算書類等の開示先や経理体制等の観点から、「一定の水準を保ったもの」とされている中小指針と比べて簡便な会計処理をすることが適当と考えられる中小企業を対象にその実態に即した会計処理のあり方を取りまとめられたものである。また、安定的に継続利用可能なものとする観点から、国際会計基準の影響を受けないものとされているため、中小指針と異なり毎年の会計基準の変更というものはない。
また、中小会計要領は、以下の観点からまとめられている
・ 中小企業の経営者が活用しようと思えるよう、理解しやすく、自社の経営状況の把握に役立つ会計
・ 中小企業の利害関係者(金融機関、取引先、株主等)への情報提供に資する会計
・ 中小企業の実務における会計慣行を十分考慮し、会計と税制の調和を図った上で、会社計算規則に準拠した会計
・ 計算書類等の作成負担は最小限に留め、中小企業に過重な負担を課さない会計
まず、経営者が活用できる会計という事があげられている。まさしく、「会社で会計を強くする」のである。
次の外部の利害関係者に対する情報提供というのはまさしく会計の役割であり、この中小会計要領に限ったものでもありません。
第三に、会計と税制の調和を図った上での会計ということは、現行中小企業の会計の現場で行われている法人税法上の処理に従った会計ということを意識しながらも法律である会社法の施行規則である会社計算規則に準拠した会計を目指すというものである。
中小企業の実態にあった会計というものの指針であるのが中小会計要領であることが上記からでも読み取れます。
中小企業の会計に関するルールは現行2つの会計に関するルールが出されている。一つは「中小企業の会計に関する指針」(以下、中小指針)、もう一つは「中小企業の会計に関する基本要領」(以下、会計要領)である。
中小指針は、上場企業が適用している会計基準の簡易版となっているため、会計基準の変更に伴い中小指針も変更されることになる。そのため、中小指針は公表されていこう毎年変更されている。
一方、会計要領は計算書類等の開示先や経理体制等の観点から、「一定の水準を保ったもの」とされている中小指針と比べて簡便な会計処理をすることが適当と考えられる中小企業を対象にその実態に即した会計処理のあり方を取りまとめられたものである。また、安定的に継続利用可能なものとする観点から、国際会計基準の影響を受けないものとされているため、中小指針と異なり毎年の会計基準の変更というものはない。
また、中小会計要領は、以下の観点からまとめられている
・ 中小企業の経営者が活用しようと思えるよう、理解しやすく、自社の経営状況の把握に役立つ会計
・ 中小企業の利害関係者(金融機関、取引先、株主等)への情報提供に資する会計
・ 中小企業の実務における会計慣行を十分考慮し、会計と税制の調和を図った上で、会社計算規則に準拠した会計
・ 計算書類等の作成負担は最小限に留め、中小企業に過重な負担を課さない会計
まず、経営者が活用できる会計という事があげられている。まさしく、「会社で会計を強くする」のである。
次の外部の利害関係者に対する情報提供というのはまさしく会計の役割であり、この中小会計要領に限ったものでもありません。
第三に、会計と税制の調和を図った上での会計ということは、現行中小企業の会計の現場で行われている法人税法上の処理に従った会計ということを意識しながらも法律である会社法の施行規則である会社計算規則に準拠した会計を目指すというものである。
中小企業の実態にあった会計というものの指針であるのが中小会計要領であることが上記からでも読み取れます。
中小企業の決算書
2013年10月23日
通常の会計では、現金並びに預金の動きをベースに売上も仕入も管理する。
しかし、期末になると税務申告用の決算のために、売掛金及び買掛金並びに在庫を把握して粗利益を求めることになる。
そうなると、期中で把握していた粗利益が期末では大きく異なってしまう。
また、経費においても現金で出ていく経費しか把握していない場合、減価償却費の計上により大きく営業利益が減ってしまう。もしくは、営業損失となってしまう。
期中の会計処理を現金及び預金取引に基づいて会計帳簿を記帳していた場合の弊害の一部をのべさせてもらいました。
決算書が収益については実現主義、費用については発生主義で作成されるのであれば、日常取引についても現金主義ではなく、収益については実現主義及び費用については発生主義に基づいて会計記帳すべきであると考えます。
その結果が、日々の記帳の成果にも続いて現状を把握し、将来の予測を可能にするからです。
経営者の長年の勘というものは非常に大事ですけれども、勘というものは人についてはうまく説明することが出来ません。
勘を数字に置き換えるためにも日々記帳し、勘が当たっていることを決算書という数字の上でもあらわすことが必要だと思います。
誰に説明するのか?
中小企業においては、金融機関に決算書を見せ融資を受けることが必要なケースが多いです。
この場合において、その時その時のつじつま合わせの決算書を出していれば、あとでぼろが出てしまい、金融機関からの信頼性がなくなってしまいます。金融機関からの信頼がなくなれば融資を容易に受けることが出来ません。
そのためにも、決算書は適正な決算書を作成し、金融機関に対してもいつでも示せるようにすることが必要になってくると思います。
決算書は税務署に提出するためではなく、社内的には将来の予測に資するために、社外的には融資を受ける金融機関の信頼を得るために適切に決算書を作成することが必要になってくると思います。
中小企業にとっての決算書を利用するのは、経営者、金融機関、税務署等の限られた利害関係者になりますので、高度な会計基準は必要ないということもいえます。
より簡便な会計基準として、『中小企業の会計に関する基本要領』(中小会計要領)があります。そして、上場会社の使用する会計基準を簡便にし中小企業に適用可能として会計基準として『中小企業に関する会計指針』(中小企業会計指針)があります。
ある程度規模の大きい中堅企業や上場を目指す企業においては中小企業会計指針を採用し、それ以外の企業においては中小会計要領に従った決算書をつくる必要があると思います。
しかし、期末になると税務申告用の決算のために、売掛金及び買掛金並びに在庫を把握して粗利益を求めることになる。
そうなると、期中で把握していた粗利益が期末では大きく異なってしまう。
また、経費においても現金で出ていく経費しか把握していない場合、減価償却費の計上により大きく営業利益が減ってしまう。もしくは、営業損失となってしまう。
期中の会計処理を現金及び預金取引に基づいて会計帳簿を記帳していた場合の弊害の一部をのべさせてもらいました。
決算書が収益については実現主義、費用については発生主義で作成されるのであれば、日常取引についても現金主義ではなく、収益については実現主義及び費用については発生主義に基づいて会計記帳すべきであると考えます。
その結果が、日々の記帳の成果にも続いて現状を把握し、将来の予測を可能にするからです。
経営者の長年の勘というものは非常に大事ですけれども、勘というものは人についてはうまく説明することが出来ません。
勘を数字に置き換えるためにも日々記帳し、勘が当たっていることを決算書という数字の上でもあらわすことが必要だと思います。
誰に説明するのか?
中小企業においては、金融機関に決算書を見せ融資を受けることが必要なケースが多いです。
この場合において、その時その時のつじつま合わせの決算書を出していれば、あとでぼろが出てしまい、金融機関からの信頼性がなくなってしまいます。金融機関からの信頼がなくなれば融資を容易に受けることが出来ません。
そのためにも、決算書は適正な決算書を作成し、金融機関に対してもいつでも示せるようにすることが必要になってくると思います。
決算書は税務署に提出するためではなく、社内的には将来の予測に資するために、社外的には融資を受ける金融機関の信頼を得るために適切に決算書を作成することが必要になってくると思います。
中小企業にとっての決算書を利用するのは、経営者、金融機関、税務署等の限られた利害関係者になりますので、高度な会計基準は必要ないということもいえます。
より簡便な会計基準として、『中小企業の会計に関する基本要領』(中小会計要領)があります。そして、上場会社の使用する会計基準を簡便にし中小企業に適用可能として会計基準として『中小企業に関する会計指針』(中小企業会計指針)があります。
ある程度規模の大きい中堅企業や上場を目指す企業においては中小企業会計指針を採用し、それ以外の企業においては中小会計要領に従った決算書をつくる必要があると思います。