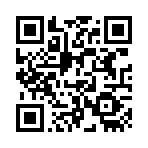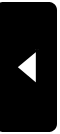中小企業の計算書類の信頼性の担保について
2014年06月26日
今日は中小企業の計算書類の信頼性の担保についてさらに考察していきたいと思います。
会社法上での計算書類の信頼性を担保する制度としては会計監査人の制度と会計参与の制度があることを先日の投稿で記載させていただきました。
会社法上はこの2つの制度により、会計の専門家による計算書類の信頼性を担保しようとしています。
しかしながら、会社法の意図するようには会計監査人や会計参与を採用する中小企業の数は少なく、結果として中小企業の計算書類の信頼性を担保するには別の手段を採用しなければならなくなっています。
しかしながら、そもそもなぜ中小企業において計算書類の信頼性を担保しなければならないと会社法が考えているのでしょうか?それは、債権者を保護する必要があるから計算書類の信頼性を担保する必要があるのです。そして、最大の債権者は誰かといえば中小企業に融資している金融機関です。この金融機関が中小企業に融資をするにあたっては、会計監査人による監査報告書もしくは会計参与の報告書の添付を条件にすれば、中小企業が会計監査人もしくは会計参与を採用し、結果として会社法の予定する会計監査人及び会計参与の制度が機能することになると考えます。
現在は、金融機関が会計監査人による監査もしくは会計参与による報告書の利用を行わないからこそ計算書類の信頼性の担保が出来なくなっているのではないでしょうか?
会計監査人による監査もしくは警戒参与の報告書がなされても中小企業の計算書類は信頼できないというのではなく、会社法の予定する制度を十分に利用し、さらにそれでも中小企業の計算書類の信頼性が高まらなければ別の手段を考えていくことが必要ですし、会社法としてもそのような制度設計を行うべきであるのでしょう。
なお、監査の格言の一つに「自己監査は監査に非ず」という言葉があります。これは監査を行うにあたっての基本であります。記帳代行を会社に提供している会計事務所が第三者に監査証明を出来ないのは、記帳代行をした結果である計算書に対して監査をすることに当たるため、自己監査は監査に非ずという原則に反するためです。
監査報告をするには、その会社の記帳業務をしてはいけないことになります。そのため、記帳業務を付随業務としておこなうことになる税理士が財務諸表に対しての意見表明が出来ない理由がここにあります。
会社法上での計算書類の信頼性を担保する制度としては会計監査人の制度と会計参与の制度があることを先日の投稿で記載させていただきました。
会社法上はこの2つの制度により、会計の専門家による計算書類の信頼性を担保しようとしています。
しかしながら、会社法の意図するようには会計監査人や会計参与を採用する中小企業の数は少なく、結果として中小企業の計算書類の信頼性を担保するには別の手段を採用しなければならなくなっています。
しかしながら、そもそもなぜ中小企業において計算書類の信頼性を担保しなければならないと会社法が考えているのでしょうか?それは、債権者を保護する必要があるから計算書類の信頼性を担保する必要があるのです。そして、最大の債権者は誰かといえば中小企業に融資している金融機関です。この金融機関が中小企業に融資をするにあたっては、会計監査人による監査報告書もしくは会計参与の報告書の添付を条件にすれば、中小企業が会計監査人もしくは会計参与を採用し、結果として会社法の予定する会計監査人及び会計参与の制度が機能することになると考えます。
現在は、金融機関が会計監査人による監査もしくは会計参与による報告書の利用を行わないからこそ計算書類の信頼性の担保が出来なくなっているのではないでしょうか?
会計監査人による監査もしくは警戒参与の報告書がなされても中小企業の計算書類は信頼できないというのではなく、会社法の予定する制度を十分に利用し、さらにそれでも中小企業の計算書類の信頼性が高まらなければ別の手段を考えていくことが必要ですし、会社法としてもそのような制度設計を行うべきであるのでしょう。
なお、監査の格言の一つに「自己監査は監査に非ず」という言葉があります。これは監査を行うにあたっての基本であります。記帳代行を会社に提供している会計事務所が第三者に監査証明を出来ないのは、記帳代行をした結果である計算書に対して監査をすることに当たるため、自己監査は監査に非ずという原則に反するためです。
監査報告をするには、その会社の記帳業務をしてはいけないことになります。そのため、記帳業務を付随業務としておこなうことになる税理士が財務諸表に対しての意見表明が出来ない理由がここにあります。
Posted by
山本公認会計士・税理士事務所
at
10:04
│Comments(
0
)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。