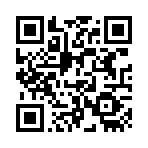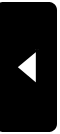中小企業の会計に関するルールについて
2014年06月19日
今日は中小企業に対する会計のルールについて述べたいと思います。
中小企業の会計のルールは、現行では「中小企業の会計に関する基本要領」と「中小企業の会計に関する指針」の2つのルールが存在します。
「中小企業の会計に関する指針」は、現行の上場会社にも適用される会計基準の簡易版というような形でした。しかしながら、「中小企業の会計に関する指針」に記載されている会計基準が実際に中小企業には適用するにはあまりにも難しすぎて実際にはほとんど適用されなかったようです。
そこで、広く中小企業にも実際に適用できるようにと「中小企業の会計に関する基本要領」が新たな中小企業の会計ルールとして制定されました。この「中小企業の会計に関する基本要領」は、実際中小企業で行われている法人税法に準じた会計処理との親和性も考慮されているため、会計のルールとして作成されているため、ほとんどの項目で多くの中小企業に適用できることとなると思います。
ただ、「中小企業の会計に関する基本要領」において、実際に中小企業に適用することにおいて難しくしているのは、「中小企業の会計に関する基本要領」Ⅰ.総論 8.記帳の重要性の存在だと思います。
8.記帳の重要性においては、適切な記帳を求めています。記帳は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従っておこない、適時に、整然かつ明瞭に、正確かつ網羅的に会計帳簿を作成しなければならないとしています。
適時に会計帳簿を作成するためには、現金出納帳については毎日の作成が求められることであり、預金出納帳や仕訳帳については最低でも1月に1回の作成が求められることになります。しかしながら、多くの中小企業でみられる会計帳簿の作成を会計事務所に委託しているようなケースでは、3ヶ月に1度記帳を行っていたり、年1度の記帳を行っているケースが多々見られます。このようなケースでは、適時に会計帳簿の作成をしているとはみなされないため、実際に適切な記帳の前提となる「中小企業の会計に関する基本要領」を適用しているとはいいがたくなります。
適時に会計帳簿を作成することは、「中小企業の会計要領」のみならず、正規の簿記の原則として当然他の会計基準も求めていますし、会社法にも求めていますが、中小業においては、実際に正規の簿記の原則が適用されているのがなかなかないので8.記帳の重要性で改めて強調されています。
「中小企業の会計に関する基本要領」で、中小企業に適用を難しくしているのが賞与引当金の計上を求めている部分と、減価償却費の部分でしょうか?減価償却費については、会計的には規則的な償却を求めていますが、法人税法は償却限度額内における任意の償却を認めています。そのため、繰越欠損が存在している場合などは減価償却を行っていない中小企業は数多くありました。この点は会計的には適切な処理とはいいがたいのですが、法人税法上このような処理を認めている点致し方ないともいえます。
「中小企業の会計に関する基本要領」を実際に中小企業全面適用するには難しい面もありますが、多くの中小企業で適用されることを望みます。
中小企業の会計のルールは、現行では「中小企業の会計に関する基本要領」と「中小企業の会計に関する指針」の2つのルールが存在します。
「中小企業の会計に関する指針」は、現行の上場会社にも適用される会計基準の簡易版というような形でした。しかしながら、「中小企業の会計に関する指針」に記載されている会計基準が実際に中小企業には適用するにはあまりにも難しすぎて実際にはほとんど適用されなかったようです。
そこで、広く中小企業にも実際に適用できるようにと「中小企業の会計に関する基本要領」が新たな中小企業の会計ルールとして制定されました。この「中小企業の会計に関する基本要領」は、実際中小企業で行われている法人税法に準じた会計処理との親和性も考慮されているため、会計のルールとして作成されているため、ほとんどの項目で多くの中小企業に適用できることとなると思います。
ただ、「中小企業の会計に関する基本要領」において、実際に中小企業に適用することにおいて難しくしているのは、「中小企業の会計に関する基本要領」Ⅰ.総論 8.記帳の重要性の存在だと思います。
8.記帳の重要性においては、適切な記帳を求めています。記帳は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従っておこない、適時に、整然かつ明瞭に、正確かつ網羅的に会計帳簿を作成しなければならないとしています。
適時に会計帳簿を作成するためには、現金出納帳については毎日の作成が求められることであり、預金出納帳や仕訳帳については最低でも1月に1回の作成が求められることになります。しかしながら、多くの中小企業でみられる会計帳簿の作成を会計事務所に委託しているようなケースでは、3ヶ月に1度記帳を行っていたり、年1度の記帳を行っているケースが多々見られます。このようなケースでは、適時に会計帳簿の作成をしているとはみなされないため、実際に適切な記帳の前提となる「中小企業の会計に関する基本要領」を適用しているとはいいがたくなります。
適時に会計帳簿を作成することは、「中小企業の会計要領」のみならず、正規の簿記の原則として当然他の会計基準も求めていますし、会社法にも求めていますが、中小業においては、実際に正規の簿記の原則が適用されているのがなかなかないので8.記帳の重要性で改めて強調されています。
「中小企業の会計に関する基本要領」で、中小企業に適用を難しくしているのが賞与引当金の計上を求めている部分と、減価償却費の部分でしょうか?減価償却費については、会計的には規則的な償却を求めていますが、法人税法は償却限度額内における任意の償却を認めています。そのため、繰越欠損が存在している場合などは減価償却を行っていない中小企業は数多くありました。この点は会計的には適切な処理とはいいがたいのですが、法人税法上このような処理を認めている点致し方ないともいえます。
「中小企業の会計に関する基本要領」を実際に中小企業全面適用するには難しい面もありますが、多くの中小企業で適用されることを望みます。
Posted by
山本公認会計士・税理士事務所
at
06:06
│Comments(
0
) │
会計
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。