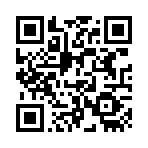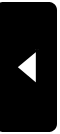現金管理の重要性
2017年07月20日
現金には、当然のごとく色も形もありません。そのため、現金取引は不正取引の温床になりやすいのです。
現金の管理が出来ていない会社は管理がずさんな会社と思われても仕方がない面があります。
また、税務調査においても現金管理が出来ていないということは粉飾が行われている可能性があるという心証を招くおそれがあります。
そこで、まずは現金管理をしっかりする必要が出てきます。
まずは、個人事業主においては、事業のお金と個人の現金とが区別がなされていないケースが見受けられます。これを防ぐためには、事業のお金を個人のお金と区別するために、手提げ金庫に事業のお金を保管するようにすべきです。そして、個人事業主の場合は、事業のお金を支払った場合は事業用のお金から支払ったことにし、一定期間、例えば一週間程度で、事業用の現金の精算を行い、事業用現金が足らない場合は事業用の預金から小口現金として引出を行うようにすべきです。
また、同族会社においても、会社のお金と代表者の現金とが区別がなされていないケースが見受けられます。これを防ぐためにも、会社のお金は個人事業主と同様手提げ金庫に会社のお金として保管するようにすべきです。そして、役員が立替払いした場合は、一定期間の後で会社の現金で精算するようにすべきです。
現金取引の多いところにおいては、売上については一日の売上金については夜間金庫もしくは翌日に預金に預けるべきです。この場合、売り上げの管理のための通帳をつくっておき、一定期間において経費用の通帳に振り替える処理を行うべきです。
経費の支払いについては、売上金の現金とは区別し、小口現金として、定期的に一定金額を預金から引き出して経費用の現金として管理すべきです。
小口現金については、毎日現金実査を行い、現金の残高を確認すべきです。
現金出納帳は、毎日つけることが望ましいですが、経費区分が未定の場合などについては一旦仮払処理を行い後日科目振替の処理を行うことも毎日つけることの方法だと考えます。
そして、現金実査の金額と現金出納帳の金額の一致しているかどうかを毎日欠かさずに確認すべきです。
売上金については、夜間金庫なり翌月銀行に預けるべきと書きましたが、そもそも、売上金から経費や仕入の支払は行うべきではありません。経費の支払いや仕入の支払はあくまで小口現金で行うべきです。
繰り返しになりますが、現金は色も形もないため、現金取引は不正取引の温床になりやすいがため、しっかりと管理を行うことが必要となってくるのです。
現金の管理が出来ていない会社は管理がずさんな会社と思われても仕方がない面があります。
また、税務調査においても現金管理が出来ていないということは粉飾が行われている可能性があるという心証を招くおそれがあります。
そこで、まずは現金管理をしっかりする必要が出てきます。
まずは、個人事業主においては、事業のお金と個人の現金とが区別がなされていないケースが見受けられます。これを防ぐためには、事業のお金を個人のお金と区別するために、手提げ金庫に事業のお金を保管するようにすべきです。そして、個人事業主の場合は、事業のお金を支払った場合は事業用のお金から支払ったことにし、一定期間、例えば一週間程度で、事業用の現金の精算を行い、事業用現金が足らない場合は事業用の預金から小口現金として引出を行うようにすべきです。
また、同族会社においても、会社のお金と代表者の現金とが区別がなされていないケースが見受けられます。これを防ぐためにも、会社のお金は個人事業主と同様手提げ金庫に会社のお金として保管するようにすべきです。そして、役員が立替払いした場合は、一定期間の後で会社の現金で精算するようにすべきです。
現金取引の多いところにおいては、売上については一日の売上金については夜間金庫もしくは翌日に預金に預けるべきです。この場合、売り上げの管理のための通帳をつくっておき、一定期間において経費用の通帳に振り替える処理を行うべきです。
経費の支払いについては、売上金の現金とは区別し、小口現金として、定期的に一定金額を預金から引き出して経費用の現金として管理すべきです。
小口現金については、毎日現金実査を行い、現金の残高を確認すべきです。
現金出納帳は、毎日つけることが望ましいですが、経費区分が未定の場合などについては一旦仮払処理を行い後日科目振替の処理を行うことも毎日つけることの方法だと考えます。
そして、現金実査の金額と現金出納帳の金額の一致しているかどうかを毎日欠かさずに確認すべきです。
売上金については、夜間金庫なり翌月銀行に預けるべきと書きましたが、そもそも、売上金から経費や仕入の支払は行うべきではありません。経費の支払いや仕入の支払はあくまで小口現金で行うべきです。
繰り返しになりますが、現金は色も形もないため、現金取引は不正取引の温床になりやすいがため、しっかりと管理を行うことが必要となってくるのです。
変動損益計算書の考え方
2017年07月19日
今日も昨日に引き続き変動損益計算書の考え方を解説していきます。
変動損益計算書においては
利益=売上-費用
=売上高-変動費-固定費
=限界利益-固定費
とあらわされますから、限界利益を高めることで利益の増加を考えていく必要があります。
また、売上高及び変動費は
売上高=販売数量×販売単価
変動費=販売数量×変動比率
であらわされますから
利益=販売数量×(販売単価-変動比率)-固定費
となります。
ここに、販売数量をあげるか、販売単価を上げるか変動比率をさげるか、固定費を下げるかにより利益を増加させるということがわかります。
ただ、販売数量をあげようとすると、販売単価に引き下げにつながりかねませんので、必ずしも利益の増加につながらない可能性もあります。
また、販売単価を引き上げるとなると、商品やサービスに対するブランド化に対する費用も必要になってくるため、一概に利益の増加につながるともいえません。
また、固定費を見直しにおいては、不要資産の売却や交通費、交際費、広告費の見直しや予算もしくは前年度実績を上回っている経費の削減などが考えられます。ただ、固定費のなかには、過去に設備投資をした設備に対する減価償却費も入ってきますので、容易に固定費を引き下げることも難しいと思って頂いていいです。
変動損益計算書の考え方は、利益計画を立てる上で目標利益に対する対策を考える上でも基礎になる考え方ですので、是非とも理解して頂きたいと思います。また、財務諸表や計算書類に添付する損益計算書で考えるよりは将来どういった対策を取ることにより損益がどのように変わるのかを予測するには変動計算書の考え方を持ちうるのは非常に有効だと思います。逆に言えば、経常利益をアップさせるには、売上を拡大させるか、限界利益率を向上させるか、固定費の見直しをすればいいことになります。
変動損益計算書においては
利益=売上-費用
=売上高-変動費-固定費
=限界利益-固定費
とあらわされますから、限界利益を高めることで利益の増加を考えていく必要があります。
また、売上高及び変動費は
売上高=販売数量×販売単価
変動費=販売数量×変動比率
であらわされますから
利益=販売数量×(販売単価-変動比率)-固定費
となります。
ここに、販売数量をあげるか、販売単価を上げるか変動比率をさげるか、固定費を下げるかにより利益を増加させるということがわかります。
ただ、販売数量をあげようとすると、販売単価に引き下げにつながりかねませんので、必ずしも利益の増加につながらない可能性もあります。
また、販売単価を引き上げるとなると、商品やサービスに対するブランド化に対する費用も必要になってくるため、一概に利益の増加につながるともいえません。
また、固定費を見直しにおいては、不要資産の売却や交通費、交際費、広告費の見直しや予算もしくは前年度実績を上回っている経費の削減などが考えられます。ただ、固定費のなかには、過去に設備投資をした設備に対する減価償却費も入ってきますので、容易に固定費を引き下げることも難しいと思って頂いていいです。
変動損益計算書の考え方は、利益計画を立てる上で目標利益に対する対策を考える上でも基礎になる考え方ですので、是非とも理解して頂きたいと思います。また、財務諸表や計算書類に添付する損益計算書で考えるよりは将来どういった対策を取ることにより損益がどのように変わるのかを予測するには変動計算書の考え方を持ちうるのは非常に有効だと思います。逆に言えば、経常利益をアップさせるには、売上を拡大させるか、限界利益率を向上させるか、固定費の見直しをすればいいことになります。
Posted by
山本公認会計士・税理士事務所
at
10:41
│Comments(
0
)
変動損益計算書について
2017年07月18日
今日は「変動損益計算書」について述べたいと思います。
利益は当然、以下の式で表されます。
利益=売上-費用
売上を分析すると
売上=販売数量×販売単価であらわされます。
また、費用を分析すると
費用=変動費(=変動費+準変動費)+固定費(=固定費+準固定費)という式になります。
利益=売上-変動費-固定費であらわされる損益計算書を変動損益計算書といいます。
ここで、変動費とは売上高に応じて変動する費用で、固定費とは売上高の増減とは無関係の費用のことをいいます。
そのため、変動費=変動比率×販売数量で表されます。
最初の利益の数式を変動損益計算書の数式に変えると
利益=売上高-変動費-固定費
=(販売数量-変動比率)×販売数量-固定費
以上の数式になります。
すなわち、この数式は固定費を上回る利益をあげることにより、正味の利益が回収できるということをあらわしています。
変動費には売上原価だけではなく、販売費も含まれることになるため、一般の損益計算書に基づいてそのまま変動損益計算書の考え方を当てはめるのは危険です。
売上原価を差し引いたという意味での粗利益が出ているから大丈夫だという事ではなく、販売費も含めた限界利益が出ているかどうかを考えるのかが大事になってきます。
限界利益とは売上高から変動費を差し引いた金額のことをいいます。
限界利益=売上高-変動費
なお、変動損益計算書はあくまで内部管理用の損益計算書であり、外部公表表の損益計算書ではありません。
ただし、変動損益計算書の考え方は、利益計画を立てる上で目標利益に対する対策を考える上でも基礎になる考え方ですので、是非とも理解して頂きたいと思います。
利益は当然、以下の式で表されます。
利益=売上-費用
売上を分析すると
売上=販売数量×販売単価であらわされます。
また、費用を分析すると
費用=変動費(=変動費+準変動費)+固定費(=固定費+準固定費)という式になります。
利益=売上-変動費-固定費であらわされる損益計算書を変動損益計算書といいます。
ここで、変動費とは売上高に応じて変動する費用で、固定費とは売上高の増減とは無関係の費用のことをいいます。
そのため、変動費=変動比率×販売数量で表されます。
最初の利益の数式を変動損益計算書の数式に変えると
利益=売上高-変動費-固定費
=(販売数量-変動比率)×販売数量-固定費
以上の数式になります。
すなわち、この数式は固定費を上回る利益をあげることにより、正味の利益が回収できるということをあらわしています。
変動費には売上原価だけではなく、販売費も含まれることになるため、一般の損益計算書に基づいてそのまま変動損益計算書の考え方を当てはめるのは危険です。
売上原価を差し引いたという意味での粗利益が出ているから大丈夫だという事ではなく、販売費も含めた限界利益が出ているかどうかを考えるのかが大事になってきます。
限界利益とは売上高から変動費を差し引いた金額のことをいいます。
限界利益=売上高-変動費
なお、変動損益計算書はあくまで内部管理用の損益計算書であり、外部公表表の損益計算書ではありません。
ただし、変動損益計算書の考え方は、利益計画を立てる上で目標利益に対する対策を考える上でも基礎になる考え方ですので、是非とも理解して頂きたいと思います。
経営計画について
2017年07月17日
今日は経営計画のことについて記載したいと思います。
自分の会社をこういった方向に持っていきたいな。大きな夢としてこういう方向性に持って行ければな。こうした夢や目標をある程度の道筋として目に見える形として落としていくのが長期計画です。壮大な夢でもかまわないと思います。
ただ、この大きな夢は遠すぎるものであるため、もう少し具体的な目標に置き換えていくのが中期計画となります。今の体制では全く夢に向かえなければ夢に向かって体制を整えていく必要があると思います。この体制を整えるのが、2~3年かかるのならば、この2~3年が中期計画の期間となります。それよりももう少しかかるでしょうというので5年計画というのが中期計画の一般的な期間になりますね。
中期計画は具体的な目標でもあるので、粗々でもいいのでもう少し具体的な目標数値が求められてくることになります。
この中期計画を達成するために、まずは目の前の目標を定める必要があります。これが短期経営計画になります。
今は経済環境の変化が激しすぎて、中期計画が立てられないと思われるかもしれません。しかしながら、自分の会社がどの方向に向かうのかを明らかにするためにも中期計画を立てることが必要です。そして、自分の会社を取り巻く環境が変われば、中期計画を見直すことも必要です。この場合に、短期計画も大幅に変える必要があるのでしたら、短期計画も見直す必要があると思います。ただ、短期計画での方向性が当初の計画時と大幅に違わないのでしたら、目の前の目標である短期計画の変更はする必要はないと思います。
会社をどういった方向に持っていくのが具体的に落とし込むためにも経営計画を立てられたらどうでしょうか?
自分の会社をこういった方向に持っていきたいな。大きな夢としてこういう方向性に持って行ければな。こうした夢や目標をある程度の道筋として目に見える形として落としていくのが長期計画です。壮大な夢でもかまわないと思います。
ただ、この大きな夢は遠すぎるものであるため、もう少し具体的な目標に置き換えていくのが中期計画となります。今の体制では全く夢に向かえなければ夢に向かって体制を整えていく必要があると思います。この体制を整えるのが、2~3年かかるのならば、この2~3年が中期計画の期間となります。それよりももう少しかかるでしょうというので5年計画というのが中期計画の一般的な期間になりますね。
中期計画は具体的な目標でもあるので、粗々でもいいのでもう少し具体的な目標数値が求められてくることになります。
この中期計画を達成するために、まずは目の前の目標を定める必要があります。これが短期経営計画になります。
今は経済環境の変化が激しすぎて、中期計画が立てられないと思われるかもしれません。しかしながら、自分の会社がどの方向に向かうのかを明らかにするためにも中期計画を立てることが必要です。そして、自分の会社を取り巻く環境が変われば、中期計画を見直すことも必要です。この場合に、短期計画も大幅に変える必要があるのでしたら、短期計画も見直す必要があると思います。ただ、短期計画での方向性が当初の計画時と大幅に違わないのでしたら、目の前の目標である短期計画の変更はする必要はないと思います。
会社をどういった方向に持っていくのが具体的に落とし込むためにも経営計画を立てられたらどうでしょうか?
月次決算について
2017年07月16日
企業が自社の経営成績を適時に把握し、自社の経営判断に生かせるためには、自計化が必要です。
そして、この自計化する意味は、記帳を会計事務所に任せていた場合、どうしても月次で決算を任せていた場合、早くて1月半後にしか月次の決算がわからないのです。これを翌月10日以内に把握するためには、一つに自社で自計化することが必要になります。
たとえば、どうしても、把握の遅れる請求書については、一定のルールを把握するように努めることが必要です。
未払の把握するためのルールとしましては、一つには、請求書を仕入先からFAXでもらうようにする。また、例えば、営業日5日までに入手できない請求書については払いを翌月回しにする。小口の消耗金については、従業員及び役員の立替払いとし、請求書とともに支払を行うようにする。この場合に、立て替え払い明細を作成し、消耗品なのか、備品なのかをまず第一次の段階で従業員に把握してもらうようにする。この立替払いにつても、月末までの分を翌営業日5日以内の提出とする等のルールづくりが必要になるのではないでしょうか?
このように自計化により月次決算を早期化することにより、月々の経営成績を適時に把握し、次なる一手を打てると思います。
そして、この自計化する意味は、記帳を会計事務所に任せていた場合、どうしても月次で決算を任せていた場合、早くて1月半後にしか月次の決算がわからないのです。これを翌月10日以内に把握するためには、一つに自社で自計化することが必要になります。
たとえば、どうしても、把握の遅れる請求書については、一定のルールを把握するように努めることが必要です。
未払の把握するためのルールとしましては、一つには、請求書を仕入先からFAXでもらうようにする。また、例えば、営業日5日までに入手できない請求書については払いを翌月回しにする。小口の消耗金については、従業員及び役員の立替払いとし、請求書とともに支払を行うようにする。この場合に、立て替え払い明細を作成し、消耗品なのか、備品なのかをまず第一次の段階で従業員に把握してもらうようにする。この立替払いにつても、月末までの分を翌営業日5日以内の提出とする等のルールづくりが必要になるのではないでしょうか?
このように自計化により月次決算を早期化することにより、月々の経営成績を適時に把握し、次なる一手を打てると思います。